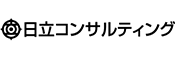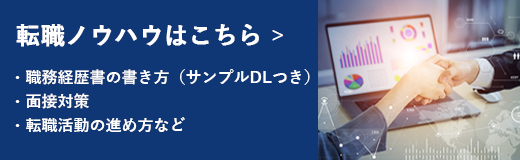※このインタビューは2025年2月に実施しました。なお、所属・肩書は当時のものとなります。
求人・採用インタビュー
最先端テクノロジーで日本企業のDXに伴走支援する、KPMGコンサルティングのDXA(Digital Transformation Acceleration)
KPMGコンサルティング株式会社

写真右から
BIG4(世界4大監査法人)の一つに数えられるKPMG。日本のメンバーファームとして監査・税務・アドバイザリーを手がけるKPMGジャパンに属しアドバイザリー分野の1つを担うのが、KPMGコンサルティング(以下、KC)です。
KCにおけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の専門家集団がDigital Transformation Acceleration(DXA)部門。データ/AIの利活用により、日本企業のDXを伴走型で支援するコンサルタントを募集しています。
別の大手グローバルコンサルティングファームも経験してきたパートナーである福島豊亮氏、室住淳一氏に、KCならではの強みや働く魅力、DXAのミッションなどについて伺いました。
追求するのは「売り上げ規模」ではなく「クライアントへの提供価値」

――お二方は別の大手グローバルコンサルティングファームにも在籍された経験をお持ちですが、KCならではの特長、働く魅力をどのように捉えていらっしゃいますか。
福島氏:大手SIerや戦略コンサルティングファームなども競合となる市場において、監査法人系ファームの良さはクライアント基盤が強固であるという点にあると思います。そして、BIG4の中でも、KPMGはコンサルティングサービスを提供するうえでのクライアント基盤が特に強いと感じています。なぜかというと、「監査」と「アドバイザリー」の間でコラボレーションを推進するカルチャーが浸透しているから。こうしたカルチャーがないと、「監査からアドバイザリーへ顧客や案件を紹介しにくい」という現象が起こり得るのです。
本来あるべき姿は、監査・税務・アドバイザリーが連携してクライアントにベストなサービスを提供することであり、各社それを目標に掲げています。しかし、コラボレーションしようとする意識がないと、連携のハードルが高くなるものです。
KCには人と人がつながりやすい風土があります。例えば、他部門に資料の提供を依頼したときなど、メールで資料が送られてきて「これを読んでください」だけで終わりません。どのような人がどのような目的で資料を求めているかを把握したうえで、理解を深めてもらえるところまでフォローするといったカルチャー、ネットワークをもっていることが強みの1つです。
もう1つの強みは、クライアントに向き合う基本スタンスです。大規模な案件ばかり追い求めるのではなく、品質が高い仕事を積み重ねていくことでクライアントにKCのファンになっていただき、長くお付き合いを続けていくことを目指しています。
少し前までは「いたずらに規模を追わない」という表現をしていましたが、とはいっても実際に規模が拡大しつつありますので、最近は「健全に成長すること」を掲げています。「大きな仕事を取ろう」と、遂行できるか分からない案件を抱え込むことを繰り返し、大きな負荷がかかって疲弊していくのは、従業員にとって幸せではありません。私たちは、クライアントからの信頼を第一に、クライアントにとって真の成長となるような支援をする。そのためには、時にはクライアントに苦言を呈する場面も出てきます。ここが他社と異なるスタンスです。
たとえば、コンサルタントがクライアントと対話し、「これ良いね、やろう」と合意すると、会社に持ち帰って上司に話しますよね。そのとき、第一声で「予算は?」と返されることがあるかもしれません。ですが、私たちは「この内容ならクライアントにとって価値があるね、やってみよう」という議論から入ります。これから先、今より規模が拡大したとしても、このスタンスは守り続けます。
室住氏:確かに、売り上げを追う企業の場合、自社が経験したことのないテクノロジーを、デスクトップリサーチだけでクライアントを説得して受注してしまうことがありがちですね。その結果、トラブルも起きやすい。KCでは、やみくもに売り上げを追わないので、クライアントに対して「できないこと」「できるかもしれないけれどリスクがあること」をしっかり説明したうえで進めるので、プレッシャーは少ないですね。
AIやデータの利活用分野はすさまじい勢いで拡大していますから、わずか1ヶ月で様相が大きく変わることもあります。KCでは、テクノロジーの可能性を語る一方でリスクの説明責任も果たし、クライアントの納得を得ながら進めていきます。そして、最終目標として、自分たちの利益だけではなく、クライアント企業に「バリューアップ」「健康な状態への回復」「さらなる成長」といった価値提供ができたかどうかを大切にする文化が根付いていると感じます。
福島氏:だからこそ、クライアントと「仕事の切れ目が縁の切れ目」にならないのです。継続して相談をしてもらえる間柄になることの方が多いのです。
データ/AIの利活用、ガバナンス支援で、企業の変革を加速させる

――DXAについて、立ち上げまでの経緯とミッションをお聞かせください。
福島氏:私がKCに参画した2017年当時、「Digital Labor Transformation(DLX/デジタルレイバートランスフォーメーション)」という部門があり、当時KCが得意としていたRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を主に扱っていました。しかし、RPAの普及にともなって導入ハードルが下がり、RPA以外の自動化ソフトも続々と出てきたため、コンサルタントの役割として次のステージに進み、2018年~2019年には「Intelligent Automation(IA/インテリジェントオートメーション)」の概念を提唱しました。業務を自動化し、さらに「考える」ことを、今でいうAI、当時では「コグニティブ」が助けてくれる世界です。世間ではDXという言葉が登場していましたが、本質的にはそれと非常によく似たものでした。その後、戦略・組織・業務、全ての観点にデジタルを沁み込ませていくサービスとして、2021年、IAからDXAへ名称を変更しました。AはAcceleration(アクセラレーション)で、つまりはDXの推進・加速です。当時、業界で「DX」を冠してDX推進のミッションを課した専門チームを備えたのは、KCだけでしたね。
今やDXのジャンルはかなり広がっていますが、そのなかでも大切にしなければならないパーツとして「データ/AI」に着目。「データドリブン経営を実現するために必要なことは何か」という問いに対してアドバイスをするために作ったのがこのチームです。
――室住さんは「CAIOの設置」を提唱されているそうですね。どのような思いを抱いていらっしゃるのでしょうか。
室住氏:多くの日本企業において、AIの利活用に関する権限・責任は「CIO」「CDO」あるいは「CDXO」と呼ばれる方々が担っているのではないでしょうか。DXの要素には、AI、データ、IoT、RPA、5Gなど複数の要素がありますが、その中でもAIの重要性が非常に高まってきました。AI開発競争が激化する現在、「このAI技術を信じてよいのか」「この技術はまだ先かもしれないが取り組んでおくべきではないだろうか」「ガバナンス上、どのようなアーキテクチャーにすべきか」など、検討すべきことが数多くあります。多くの企業はIT部門やDX部門にAI活用推進を委ねていますが、AI技術は、より専門的な知識と経験による課題への対応が必要であり、専任での管理・統括の必要性が増してきています。
そのため、AI戦略立案からユースケース創出、AI投資実行判断、AIリスク・ガバナンス整備・運用、AI・データ利活用人材の育成、AI・データマネジメントプラットフォーム構築、社内外ステークホルダーとの連携などを総合的に担うCAIO(最高AI責任者)が要請されてきていると考えます。
こういった背景から、私たちとしてはその取り組みを補完するサービスを提供しています。必ずしも「CAIOを設置すべき」と言っているわけではなく、CIOやCDOでも、あるいはそうしたCxOがまだいない企業であっても、データ/AI の利活用を進めようとすると必ずぶつかるアジェンダを乗り越える支援をするのが、私たちのやりたいことなのです。
具体的には、AIの活用をはじめ、AI活用リテラシーの向上、AIを作る人材育成、AIを社内に浸透させるチェンジマネジメントを担える人材の育成など。社内にケイパビリティがなければ、たとえばスタートアップや別のAIベンダーと組むアライアンス戦略を考えるなど。企業が自立自走できるようになるまで伴走し、支援したいと考えています。
さらにいえば、予算編成の在り方についても問題提起をしたいです。多くの日本企業は期初から遡って3~4か月前に次年度予算を策定しますが、そこでデータ/AI利活用の予算を決めてしまうと、それこそChatGPTのようなものがいきなり現れたときに対応できないでしょう。「来年は予算をとって行いましょう」ではもう遅い。だからCAIOが執行できる予備予算(AI戦略実行基金、AI技術開発予備費、先端技術導入促進費等)も策定し、急進的な技術が出現したとしてもスピーディに執行し、実行していけるようにすべきと考えています。
――CAIOアジェンダを支援していく上での課題としては、どのようなものを想定しているのですか。
室住氏:私見ではありますが、「ガバナンス」が重要です。AIガバナンスに自信がないから、新しい技術の採用に踏み出せない企業は多いですね。「すごいエンジンを積んだ車に乗れるけど、これは日本の公道を走っていいのか?」といったようなジレンマにさいなまれていると思います。AIガバナンスについては、KPMGとして品質の高いデリバリーができる自負があります。AIガバナンスを効かせることでリスク管理がしやすくなり、安心してデータ/AI利活用を促進できるように、ジレンマをときほぐしながら解決していきます。
「失敗を恐れるな」ではなく「失敗しなさい」の風土で新たなチャレンジを

――DXAをどのような組織にしたいのか、どのようなコンサルタントであってほしいのかをお聞かせください。
福島氏:今はAIのコンサルティングニーズが高いですが、「民主化」といわれるように誰もが扱えるようになっていくでしょう。これまでコンサルタントに求めていたアドバイスも、AIを活用すればクライアントは自分で手に入れられるようになる。だから私たちはより専門性を高め、会話のレベルを高めていく必要があります。そしてKC内においても、DXAは新しいテクノロジーを採り入れて各部署で使える武器を作るミッションを担っています。従って、チームに所属するメンバーには、常にアップデートができる人、アンテナが高い人であってほしいですね。そのアンテナは皆同じ方向でなく、さまざまな方向に向いているのがいい。アンテナの方向が360度に近い組織であれば、アップデートできる確率が高まるでしょう。
そして、アンテナが高くアップデートに前向きな人が、安心して新しいことに取り組める場を作るのが私の仕事だと思っています。私は毎年、年初に「皆、失敗しなさい」と言っているのです。「失敗を恐れるな」ではなく「失敗せい」と。1年間平穏無事で、すべてが優秀でした…というのはおかしいし、必ず何か失敗しているはず。していなかったとすれば、それはチャレンジしなかったということだよね、と。
新しいことに挑戦してつまずくことを許容していますし、「ピープルケア」と呼ぶフォロー体制も整えています。「最近少し困っている」から、シビアな悩みまでヒアリングを行い、そのメンバーのパフォーマンスマネジャー――いわばメンター役のような存在、さらには担当パートナーがケアします。不調だけでなく、「実現したいキャリアに向け、やりたいことができているか」といった観点でも、成長に責任を持つ仕組みになっているのです。
室住氏:コンサルタントは、「企業の医者」として、クライアントの健康状態を正確に把握し、しっかり解決できる存在でなくてはなりません。しかし、ともすると「この病気を自分の得意分野だけで治したい」という人が出てくることがあるのです。それでは過剰品質になることもあるし、まったく見当違いのサービスを提供することにもなりかねないでしょう。目的を見据えたうえで、このクライアントにとって一番大切なのは何かを考えて価値提供できるプロフェッショナルであってほしいです。
――お二方が考えるDXAの魅力とはどのようなところでしょうか。入社を検討している皆さんにメッセージをお願いします。
室住氏:それぞれが自分の専門分野・得意分野を持っていて、主張もするけれど「それは目的に沿っていないのではないか」「すごい技術だけど今必要ではないよね」というアドバイスをくれる人たちが周囲にいて、「腹落ちするまでディスカッションしよう」という雰囲気があります。風通しがとてもよいですね。クライアントの課題解決のため、別の専門領域の方が適しているとなれば、しっかり連携します。そうしたチームワークの良さが魅力だと思います。福島氏:この組織で働く魅力は、私がいること、そして室住さんがいることですね(笑)。次に、新しいことにずっとチャレンジし続けられること。DXの専門家は、手がけるものが常に変わる。その変化を体験できるのが大きな魅力です。失敗して当たり前、減点法ではなく加点法の文化の中で、チャレンジを楽しんでほしいと思います。
ハイクラス転職を実現する
「コンサルタントの提案」
をぜひご体験ください
ハイクラス転職で求められることは、入社後すぐにビジネスを牽引する存在になること。
そのために「コンサルタントの提案」を聞いてみませんか?
ご経験・ご経歴・ご希望などから、転職後のご活躍イメージを具体的にお伝えします。