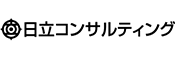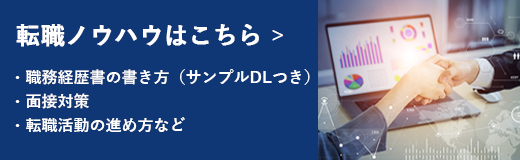※このインタビューは2025年1月に実施しました。なお、所属・肩書は当時のものとなります。
求人・採用インタビュー
インクルーシブネスで、クライアントと社会の未来を形づくる――EYSCの成長をけん引する「揺るぎないDE&I」
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社

- EYSC DE&I Leader パートナー 佐々木 惠美子氏
- EYSC DE&I Leader パートナー 井上 淳氏
-
EYストラテジー・アンド・コンサルティング(以下EYSC)の強みの一つは、多様なバックグラウンドを持つ人々が集結し、互いの強みを掛け合わせながら成長している点にあります。その背景には、グローバルで培われてきた「DE&I(Diversity, Equity & Inclusiveness = 多様性、公正、包摂)」の文化がしっかりと根付いていることが大きいでしょう。
本記事ではEYSCのDE&Iをリードするパートナーの2人にインタビューを実施。DE&Iを「組織成長に不可欠な重要戦略」と捉える同社が、どのような思いで施策を展開し、多様な人々を生かしながらビジネス成長を図っているのでしょうか。JAC Recruitmentのコンサルタントがお話を伺いました。
写真左から
多角的な知見が必要だからこそ、求められる多様性
――まずはEYSCにおけるDE&Iの位置付けや考え方についてお聞かせください。
 EYSC DE&I Leader パートナー 佐々木 惠美子氏
EYSC DE&I Leader パートナー 佐々木 惠美子氏
クライアントの課題も多様であれば、解決を支援するコンサルタントも多様でなければ対応できませんし、チームでプロジェクトを進める以上、互いを認め合い多様性を力に変えるインクルーシブな組織を作らないと成果は出せない。その結果、EYSCの成長にもつながる。そこに企業として本気で取り組む姿勢が現れていると思います。
こういった取り組みは単に「女性活躍推進が注目されているから」とか「障がい者雇用率を達成しないといけないから」という外的な要因ありきで動き始めたわけではありません。むしろ組織成長のための必然としてDE&Iを推進してきた、という感覚なのです。
井上氏:私自身のキャリアは、男性中心の文化が色濃かった銀行業界がスタートで、そこで10年超勤務しました。そこから一転してコンサルティング業界に移り、M&AのFAS領域、さらに監査法人やコンサルファーム出身のメンバーが入り交じるEYSCで仕事をしてみると、本当に多種多様な人がいると感じます。
もちろん「多様性を認め合おう」というのは簡単ですが、実際の現場では異なる意見が活発に議論され、より良い成果につなげていくための仕組みやカルチャーづくりが必要です。よく言われるように、DE&Iは単に理念として掲げるだけではまったく足りません。日々の業務のあらゆる場面でDE&Iが体現されるようにしっかり実行に移してきたのがEYSCらしさだと考えています。
「選ばれる職場」に向けて、メンバー間ネットワーク×トップダウンで仕組みづくり
 EYSC DE&I Leader パートナー 井上 淳氏
EYSC DE&I Leader パートナー 井上 淳氏
――EYSCにおけるDE&I推進体制について具体的に教えてください。
佐々木氏:マネジメントや人事だけではなく、メンバー主導のネットワークや各ビジネスユニットが連携しながら推進しているのが特徴的です。さまざまな立場のメンバーが集まってDE&Iを議論することで、より実効性のあるアイデアが生まれると考えているためです。EYでは、ジェンダーやLGBT+、マルチカルチャー、障害などをテーマとした社内コミュニティがいくつもあり、そこに所属するメンバーが自発的にネットワークづくりや社内外の理解促進を推進しています。私たちマネジメントは、その活動を一方的に押し付けるのではなく、メンバー同士のネットワークを尊重しながら、全力でサポートする立場として関わります。
例えば「育児や介護と仕事の両立をする際のハードル」、「外国籍メンバーが日本で働く上での悩み」や「障がいのあるメンバーやご家族がどのような課題を抱えているか」といった声が経営陣まで上がってくる。すると、私たちが具体策を検討し、人事チームと連携しながら新しい制度設計に反映します。
さらにDE&I関連のデータや施策の進捗は、経営会議でも逐一共有されます。そこに各ビジネスリーダーも参画し、「私たちのチームで取り組める余地は?」と考えて自発的に動き始めて輪が広がっていく。
こうしてトップダウンとボトムアップを両面で回す仕掛けがあるため、さまざまな制度が整備されてきたのだと思います。
井上氏:EYSCの面白いところは、DE&I推進を専業化した部署をあえて設けていないことです。人事部門内にDE&Iを専任で見るメンバーはいますが、私や佐々木のようにM&AやコンサルティングなどのビジネスラインのリーダーがDE&Iリードも担う、というのが基本的な方針です。
いわゆる「DE&I推進室」のような部署を作ってしまうと、「これはそこの部署の仕事でしょ」と周囲にひとごとと受け取られやすい面もあります。DE&Iは日々の業務やチーム運営、制度の運用などで現場感覚を持ちながら、地道に浸透させるしかありません。その意味では、経営会議に出席しているパートナーがDE&Iも担い、各ビジネスの責任者を巻き込んでいくやり方は理にかなっていると思います。
佐々木氏:ビジネスの場面においても、当社では1人ではなく複数のパートナーがそろってお客さまのもとへ伺うようにしています。お客さまの抱える課題も複雑化している中で、個々のパートナーが持つ多様な知見を集約してサービスを提供することを心掛けています。また、私たちの支援を通じて、お客さまはもちろんのこと、その先の社会やステークホルダーへの価値提供にも目を向けられるコンサルタントであるべしというのが当社の考え方です。そういった考えを実行に移す上でもおのおのの専門性を最大限に生かすためのコラボレーションは欠かせないものであるため、意識的に組織全体に浸透させてきた経緯があります。
両立支援のアップデート――現場の声から生まれる新施策
――EYSCは以前から制度が充実しているイメージでしたが、新たにアップデートされたものもあるのでしょうか。
佐々木氏:実は私自身も制度面は十分整っていると思い込んでいた時期がありました。ところが、女性メンバーとの座談会などで「両立支援制度などについては他社と比べると実は後れをとっている部分がある」という声を受け、衝撃を受けたのです。改めて調べてみると、たしかに細部が今のニーズに即していなかったり不足していたりするところが見つかりました。
そこで急いで制度の見直しを図りました。その一例が「ライフサポート休暇」です。これは家族のケアや自身の健康に関する幅広い事由で休暇が取得できるセーフティネットのような制度です。この制度は元々「看護休暇」からアップデートしたものですが、旧制度ではカバーしきれていなかった多様な家族の形への対応、自身の長期治療が必要な疾病や障がい、生理・更年期・不妊治療、性別移行等に係る事由でも広く有給を取得できるようにしました。制度を設けたことで、座談会でヒアリングしなかった多くのメンバーからも「今まで声を上げる機会がそれほどなかったが、本当に助かった」といった意見が多く寄せられました。
井上氏:両立支援は法令で定められた制度だけ整えればいい、という話ではありません。社会や個人のライフスタイルがめまぐるしく変化する中で、企業側もメンバーがサステナブルに活躍し続けられるよう常にアップデートし続ける必要があります。実際に現場のメンバーと対話をすると、両立する上での状況やニーズも非常に多様化してきていることを感じます。そのため、EYSCでは、さまざまなケースに対応できる柔軟な選択肢を用意し、メンバーが自らの境遇に応じて自律的に働き方をデザインできることを目指しています。
このような制度設計においても、メンバー間のネットワークやアンケートなどを通じて得た「現場の声」に素早く対応していく仕組みが確立されている。ここは会社の大きな強みだと思います。
課題と向き合い、長期的に変えていくための「焦らない」戦略

――さまざまな企業がDE&Iに関して、特に女性の役員・管理職に関する目標数値を掲げています。お2人は現状について、どのように受け止めていますか?
井上氏:役員や管理職層の女性比率はまだ十分ではないと認識しています。業界的には一般企業よりは高いものの、意思決定層における多様性向上にはまだまだ課題が残っているため、中長期的な数値目標は掲げています。
ただ、「数値目標を満たすために採用や昇格における女性の人数枠を作る」といった形での対応は行っていません。この課題を解決するためには、何がギャップを生み出す要因となっているのかを丁寧に分析し、既存の仕組みや文化の変革を粘り強く行わないことには本質的な解決にならないと考えているからです。社内で生じ得るギャップについては丁寧なレビューを行いつつ、採用や評価、昇格においては公平性を期しています。例えば、メンバーがライフイベントでキャリアを中断した場合は、復職後のキャッチアップや両立サポートは用意しますが、その上での昇格考査はあくまで同じ評価軸で判断しています。
佐々木氏:男性が母集団として多いため、企業の規模が大きくなるにつれて、女性メンバーや役員の比率の面では苦戦する傾向にあるのは事実です。ただ、だからといって目下の数字に躍起になるのではなく、焦らずに私たちの方針に基づいて継続的なサポートを絶やさないことで、着実に変化していることも実感しています。
また、ジェンダーギャップは重要な社会全体の課題でもあると認識しています。ジェンダーギャップ指数を見ると、日本が特に遅れているのは政治・経済分野で、中でも企業女性管理職比率は非常に低い状況です。教育分野は比較的順位が高い中で、社会に出るとバリアーが一層高まるという現状を改善することは、次世代に向けてビジネスが持つべき社会的な責任があると感じています。個社の取り組みだけでは解決が難しい面もありますので、産官学が手を取り合いながら推進していくことが重要ですし、企業や業界の発展を支えるファームとして、EYが解決をリードする存在となることを目指していきたいです。
インクルーシブなチームづくりと定着への道
――そうした社内でのインクルーシブなカルチャーは、どのように育まれているのでしょう?
井上氏:多様性というと、どうしても特定の属性やバックグラウンドによる違いという印象を持たれがちです。しかし実際には、ほぼ同じバックグラウンドに見えるメンバー同士でも考え方が違うということもしばしばあります。私の部門では会計士資格を持つメンバーが多いので、同様の人たちの集まりに見えつつも、周辺スキルには個々に差があり、それが多様性へとつながっています。
さらに言えば、環境や状況が変われば、人はマジョリティ側にもマイノリティ側にもなり得ます。実際に国内では日本人としてマジョリティにいると思っていても、海外に出ればマイノリティに変わるわけですし、同じ環境にいてもライフステージの変化でマイノリティ性を持つことも出てきますよね。インクルーシブなカルチャーとは、一人一人が多様性の中にいることを理解し、全員がビロンギングを感じられるようにサポートし合う信頼関係の基盤なのだと思います。
EYSCでは、インクルーシブ・コミュニケーション・トレーニングという研修を実施しているのですが、ここで重要な出発点は、「マイノリティやアウトサイダーの立場になったときの経験に対する共感」です。誰しも心の中に持つ「自分らしくいたい」「認められたい」といった感覚をお互いに気付き、自分の立場でできることを考えるところからカルチャーの醸成は始まるのだと思います。
佐々木氏:私は「この人ちょっと高圧的かな?」と思う相手でもあまり圧を感じず、「こういうタイプのコミュニケーションをする人なのだな」と受け入れるほうです。先に相手を否定するのではなく、まずは共感する。その上で、共通の目的を持ってどう擦り合わせるかを一緒に考える――この姿勢が大事かなと思います。
強いリーダーシップを発揮する人ほど、実は自分のチームにいろいろな意見を採り入れたい場合もあります。彼らが気付かない部分をサポートするだけで、「違い」を「価値」に変えていけるのではないでしょうか。
――これまで伺ったプロセスを経て、最終的にどういう状態を目指しているのでしょうか。
佐々木氏:KPIの一つとして、私たちはInclusiveではなく、Inclusiveness――つまり包摂に向けた取り組みではなく、包摂が定着している“状態”を目指しています。例えば、単純に女性のパートナーの数を増やすことがゴールではなく、意思決定層にいるマネジメントの多様性を高めて多様な視点が生かされ、より良い意思決定につなげることが重要なのです。普段から活発な議論ができる状況がビジネス上欠かせない業界だからこそ、Inclusivenessであることに意味があると考えています。社会変化に合わせて常にアップデートするDE&I

――最後に、EYSCへの転職を考えている方にメッセージをお願いします。
井上氏:「人は人生の中で、何度でもキャリアやライフステージが変わる」と私は思っていて、それに対して柔軟に寄り添ってくれる制度や風土を会社が用意できるかどうかは非常に重要だと考えています。
EYSCはまさにそこを絶えずアップデートしていますし、私たちDE&Iリードパートナー自身も「さらに改善できないか」とアンテナを張り巡らせています。同じライフステージが長く続くということは考えにくい状況の中で、さまざまなライフイベントやキャリアの分岐点に対応できる柔軟性を持った環境の構築を目指しています。ぜひ安心して飛び込んでいただき、ここでしか得られない多彩な経験を積んでいただけたらうれしいですね。
佐々木氏:私たちは、DE&Iを「硬直化したもの」ではなく、一人一人の声に耳を傾けて「動的に変化するもの」として捉えています。メンバーからのフィードバックや社会情勢に合わせてルールや制度を更新するのはもちろん、特定の背景を持つ方だけを特別に扱うのでもなく、一人一人の違いをきちんとケアして、正当に評価することを重視しています。
多様なバックグラウンドを持つメンバーと共に新しいビジネスを切り開いていきたい方、そして「自分らしさ」を生かしながらキャリアを築きたい方には、EYSCを選んでいただく価値があると思います。私たちも、あなただけの強みや個性と出会えるのを楽しみにしています。
ハイクラス転職を実現する
「コンサルタントの提案」
をぜひご体験ください
ハイクラス転職で求められることは、入社後すぐにビジネスを牽引する存在になること。
そのために「コンサルタントの提案」を聞いてみませんか?
ご経験・ご経歴・ご希望などから、転職後のご活躍イメージを具体的にお伝えします。