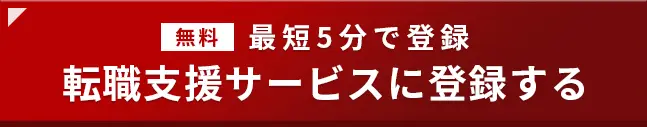スペシャリストとしてのキャリアを歩むことを考えている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、スペシャリストとしての力が必要とされやすい仕事や転職時のポイント・キャリアプランを解説します。
転職を検討中ですか?
今現在、
- 自分の市場価値を知りたい
- 今後のキャリアをどうするか整理したい
- 転職活動を無駄なくスムーズに進めたい
上記のようなお困りごとがございましたら、私たちJACへ相談してみませんか?
転職活動の進め方を相談する転職を検討中ですか?
今現在、
- 自分の市場価値を知りたい
- 今後のキャリアをどうするか整理したい
- 転職活動を無駄なくスムーズに進めたい
上記のようなお困りごとがございましたら、私たちJACへ相談してみませんか?
転職活動の進め方を相談する
目次/Index [非表示]
スペシャリストとは
本章ではスペシャリストの定義と、スペシャリストと混同されることの多い「ゼネラリスト」「エキスパート」「プロフェッショナル」との言葉との違いについて解説します。
スペシャリストとは、特定分野における高い知識・技術・経験を備えた専門家
スペシャリストとは、特定の分野や職務において高度な知識や技術を持ち、自身の専門性を発揮して新たな価値を創造したり、企業の成長に寄与したりする人材のことを指します。
スペシャリストとゼネラリストの違い
スペシャリストは、特定の分野に特化し、深い知識と高度なスキルを持つ人材を指すのに対し、ゼネラリストは、幅広い分野にわたる知識やスキルを持ち、多岐にわたる業務に対応できる汎用性の高い人材のことを指します。
多くの場合、スペシャリストは特定分野の課題解決や技術提供に貢献する役割を担い、1つの技術や知識を深く追求する傾向があります。一方ゼネラリストは、異なる領域をつなぐ役割や総括的な役割を担うことが多く、各技術や知見を戦略的に組み合わせてプロジェクトを推進したり、組織を運営したりします。
スペシャリストとエキスパートの違い
エキスパートとは、一般的にスペシャリストがさらに経験や実績を積み上げ、専門性に磨きをかけた存在であり、特定分野の中でも専門性を突出して極めた人材を指します。
スペシャリストとエキスパートはどちらも特定の分野において高い能力を持つ専門家を指す言葉として使用されますが、スペシャリストよりもエキスパートのほうが豊富な経験や実績を有し、市場価値が高くなる傾向があります。
スペシャリストとプロフェッショナルの違い
スペシャリストとプロフェッショナルはどちらも、特定分野において専門知識やスキルを備え、自身の専門性を活かした職業に就いている人材を指します。
ただし、プロフェッショナルは、単にスキルや知識だけではなく、社会の一員として高い倫理観を持ち、社会的な責任を果たしながら、自身の専門分野で活躍している点が大きな特徴です。
スペシャリストとしての力が必要とされやすい仕事・職種
本章では、スペシャリストとしての能力が必要視される傾向がある次の7種の仕事・職種について、なぜスペシャリストとしての力が必要とされやすいのかを解説します。
● マーケティング職
● エンジニア・技術職
● クリエイティブ職
● 財務・会計系職
● 研究・開発職
● 金融系専門職
● 医療系専門職
マーケティング職
マーケティング職においてスペシャリストとしての力が必要とされる理由は、データ分析や心理学、デザインなど、さまざまな分野の知識を駆使することが求められるほか、消費者の心を捉えるクリエイティブなアイデアを生み出していかなければならないからです。
具体的な業務としては、市場調査や商品企画、広告宣伝、販売促進などがあり、変化する市場や消費者の動向とニーズを汲みながら売上の拡大に取り組みます。
エンジニア・技術職
エンジニア・技術職は、製品やシステムの設計、開発、製造、メンテナンスなどを行う仕事であり、業務の遂行にあたって専門的な知識が必要であることから、スペシャリストとしての力が求められる傾向があります。
一口にエンジニア・技術職と言っても、ソフトウェアエンジニアをはじめ機械設計エンジニアやインフラエンジニアなどさまざまな職種があり、それぞれがスペシャリストとしてより細かな領域の知見・スキルを有しています。
クリエイティブ職
クリエイティブ職は、デザインや映像、音楽など、創造性を活かして作品を作り出す仕事です。斬新なアイデアを生み出し、それを形にする能力が求められるほか、最新のトレンドや技術を自分のスキルとして習得する勤勉さも不可欠です。
Webデザイナーや動画クリエイターなどの職種があり、トレンドや最新技術、クライアントの要望を形にする技術力などのスペシャリストとしての力が必要とされる傾向があります。
財務・会計系職
財務・会計系職は、企業の財務戦略を支え、正確かつ適切な会計処理や資金管理を担う職種です。具体例として、公認会計士や税理士、ファイナンシャルアナリストなどの専門職のほか、企業の財務職や会計職などが挙げられます。
専門知識の欠如は企業経営に大きな影響を与えかねません。また、業務の遂行においても不可欠です。財務・会計系職に就くためには、専門的な会計処理に関する知識や財務経験、法律などへの深い理解が求められます。
研究・開発職
研究・開発職は、新しい製品やサービスを開発するために、研究や実験を行う職種です。専門分野に関する深い知識はもちろんですが、新しい発見や開発に寄与する探究心や想像力も不可欠です。さらに技術的な知識だけでなく、研究成果をビジネスにつなげるための観点が求められることもあるでしょう。
研究や開発にあたっては、特定の分野の知識が必要になることから、スペシャリストとしての力が必要視されます。
金融系専門職
金融系専門職は、金融商品を取り扱い、顧客に金融サービスを提供する仕事です。金融市場は社会情勢の変化に伴い常に変動しており、最新の市場情報を分析した上で、迅速で正確な意思決定が求められます。
迅速で正確な意思決定を行うためには、相応の専門知識が必要になるため、金融系専門職においてもスペシャリストとしての力が求められる傾向があります。
医療系専門職
医療系専門職は、患者に医療行為を行う職種であり、具体例として、医師や薬剤師、リハビリテーション職などが挙げられます。
医療系専門職に就くためには、資格が必要になる場合が多く、資格取得の際に専門的な知識を習得しなければなりません。また、業務遂行にあたっては、生命に直結する実務を担うケースが多く、正確性と深い専門知識が欠かせないため、スペシャリストとしての力は不可欠な職種と言えるでしょう。
スペシャリストが注目されている理由
転職市場においてスペシャリストが注目されるのには、主に次の4つの理由が挙げられます。
● 終身雇用制度の崩壊
● DX浸透による社内業務効率化
● 企業課題・顧客ニーズの複雑化
● 技術の高度化・テクノロジーの発展
ここでは、なぜスペシャリストが注目されているのか、各理由について解説します。
終身雇用制度の崩壊
スペシャリストが注目される理由の1つに、終身雇用制度の崩壊が挙げられます。
かつての日本は、採用した人材を定年までジョブローテーションさせながらゼネラリストを育成する人材戦略が主流でした。しかし、終身雇用制度が崩壊しつつある現在、キャリア形成が企業任せではなく、個人の責任に委ねられるようになりました。
終身雇用制度の崩壊を背景にスペシャリストになる必要性が高まりつつある点が、スペシャリストへの注目を集める理由になったと考えられます。
DX浸透による社内業務効率化
デジタルトランスフォーメーション(DX)による社内業務効率化が進展していることも、スペシャリストが注目される理由の1つとして挙げられます。企業のDX化に伴い、単純労働やルーティンワークが自動化され、より高度な判断力や専門的知識を持つ人材が必要とされるようになりました。
企業課題・顧客ニーズの複雑化
企業が抱える課題や顧客が求めるニーズは、時代の流れとともに複雑化する一方で、課題解決にあたっては迅速な対応が求められています。このような社会背景もあり、企業は特定分野における深い知識と経験を持つスペシャリストを雇用することで迅速かつ的確に課題解決や顧客ニーズに応対するようになりました。
企業課題・顧客ニーズの複雑化によりスペシャリストを求める企業が増えたことも、スペシャリストが注目される理由と言えるでしょう。
技術の高度化・テクノロジーの発展
技術の高度化とテクノロジーの発展は、スペシャリストの需要を加速させる一因になっているでしょう。AIやIoT、バイオテクノロジーなど、新たに登場した技術やテクノロジーに対しては、一般的な知識やスキルだけでは対応できません。
企業が市場での競争優位性を保つことを目的に新たなテクノロジーを取り入れるためには、その分野に特化したスペシャリストの力が不可欠です。このように技術の進展によりスペシャリストの需要が増加したことも、スペシャリストが注目される背景にあると考えられます。
スペシャリストに向いている人の特徴
本章では、スペシャリストに向いている人として挙げられる、次の5つの特徴について解説します。
● 特定分野への強い興味関心を持つ
● 没頭し突き詰めて考える習慣がある
● 自分なりの課題解決のやり方を持っている
● 常に専門分野の最新情報を収集している
● 仮説思考で物事に向き合う癖がある
特定分野への強い興味関心を持つ
スペシャリストに向いている人の特徴として、特定分野への強い興味関心を持つ人材が挙げられます。
スペシャリストは高度な専門知識が求められるため、特定分野への強い興味関心が継続的な学びと成長を支える原動力になるでしょう。
例えば「幼少期から科学に興味があり、趣味で実験を続けていた」「システム開発に興味があり、独学でプログラミング言語を習得した」など、特定分野に対して深い興味を持つ人はスペシャリストに向いている可能性があります。
没頭し突き詰めて考える習慣がある
一つのテーマや課題に没頭し、突き詰めて考える習慣がある人は、高度な専門性を培える素養を備えている可能性があります。スペシャリストは自身が専門とする分野を深く理解する必要があり、探究心を持ち粘り強く学ぶ姿勢が不可欠です。
「時間を忘れるほど1つのことに集中し続けた経験がある」「難題に対してあきらめず何度も解決に挑戦した経験がある」などの人は、この特徴に該当するかもしれません。
自分なりの課題解決のやり方を持っている
スペシャリストは、問題や課題に直面した際、既成の知識や手法にとらわれず、柔軟な発想で課題解決に取り組める傾向があります。固定概念にとらわれず独自の視点で物事を考えられる人材は、より効率的かつ効果的な方法で問題を解決に導くことができるでしょう。
「既存のマニュアルに頼らず、自分で新しい方法を試す」「独創的なデザインや表現を発案することが好き」など、自律的な問題解決能力を有する人は、スペシャリストとして活躍できる素養を持ち合わせていると言えるでしょう。
常に専門分野の最新情報を収集している
スペシャリストとしての価値を高めるためには、常に最新の情報を探求し、新しい技術を身につける姿勢が不可欠です。特に、技術や知識が進化し続ける現代においては、最新情報に疎くなってしまうと市場における競争力を失うリスクがあります。反対に常に最新の情報を収集し、新しい技術や手法をいち早く取り入れられる人は、競合他社や他のスペシャリストと差別化を図ることができるでしょう。
日常的に専門的なニュースや論文に触れる習慣を設けていたり、専門性の高いセミナーや勉強会に参加したりしている人は、現代ニーズに即した知識・技術を身につけていると考えられます。
仮説思考で物事に向き合う癖がある
仮説思考で物事に向き合う癖がある人も、スペシャリストとしての素養を備えている可能性があります。
仮説思考は、より適切な解決策を見つけるために必須とされる能力であり、特定の分野で迅速な成果創出が求められるスペシャリストにとって不可欠な素養です。
常に物事に対して「なぜ?」と疑問を持ち、仮説を立てた上で課題解決に取り組める人は、仮説思考を活かして物事を考える能力を備えていると言えるでしょう。
スペシャリストとしてキャリアを重ねる上で必要なこと
スペシャリストとしてキャリアを重ねる上では、次の4つの取り組みが必要です。
● 定期的に社外のスペシャリストと交流を図る
● 専門領域に関する資格取得にも挑戦する
● 専門領域とは異なる立場の人の意見も取り入れる
● 専門外の業務経験も積み「T字型人材」も目指す
本章では、上記4つの取り組みについて、必要視される理由や具体的な取り組み事例を解説します。
定期的に社外のスペシャリストと交流を図る
社外のスペシャリストと交流することで、自身の専門領域における最新の動向や新しい視点を得られます。また、自分のスキルや知識の度合い・レベルを相対的に確認できる機会にもなったり、今後の自身のキャリアを考える上で社外のスペシャリストのキャリアが参考になったりすることもあるでしょう。
社外のスペシャリストと交流を図るためには、専門領域に関連するセミナーやカンファレンスに参加する、オンラインコミュニティや業界団体に加入するなどの方法があります。
専門領域に関する資格取得にも挑戦する
自身のスペシャリストとしてのキャリアを高める方法として、専門領域に関する資格取得に挑戦することも有効です。
資格を取得する過程では、体系的に専門知識を学ぶことができ、実務における遂行能力の向上に寄与することが期待できます。また資格を取得することで、自身の専門性を対外的に証明できるようにもなります。転職市場においては、取得した資格によって自身の価値や評価が高まることもあるでしょう。
なお、資格取得にあたっては、自分のキャリアプランと照らし合わせて、取得する資格を決めることが重要です。
専門領域とは異なる立場の人の意見も取り入れる
スペシャリストとしてのキャリアを高めたいと考えているのであれば、専門領域とは異なる立場の人の意見も積極的に取り入れましょう。
立場が異なる人の意見を取り入れることで、自身の専門性を新しい視点から再評価できます。また、別の角度や新たな考え方を知ることで、専門性の幅が広がり、より包括的なスキルセットが形成されることもあるかもしれません。
自身の専門領域とは異なる立場の人の意見も取り入れるにあたっては、社内の他の部署に在籍する社員や他の職務を担う社員と交流を図る、異業種交流会や異分野のプロジェクトに参加するなどの方法があります。
専門外の業務経験も積み「T字型人材」も目指す
専門外の業務経験も積み「T字型人材」を目指すのも、スペシャリストを目指す上で有効な手段です。
「T字型人材」とは、深い専門性(縦軸)に加えて幅広い汎用スキル(横軸)を持つ人材のことを指します。T字型人材になることでスペシャリストとしての付加価値がさらに高まるでしょう。
マネジメント経験を積む、後進の育成に取り組むなど、スペシャリストとは異なる角度から社会や企業に貢献できる幅広い汎用スキルを培っていきましょう。
スペシャリストの転職を成功させるポイント
ここでは、スペシャリストの転職を成功させる上で意識したい、次の4つのポイントについて解説します。
● 専門領域外の人でも分かる粒度で言語化する
● 転職先候補の企業文化や雰囲気を理解する
● 求人ポジションにおける業務イメージを擦り合わせる
● 周囲と連携しながら成果を出したエピソードも伝える
専門領域外の人でも分かる粒度で言語化する
転職活動では、専門領域外の人でも分かる粒度で言語化することが重要です。
面接などで相対する採用担当者や面接官は、必ずしも専門知識を有しているとは限りません。特に、スペシャリストが持つスキルや経験は専門性が高いため、一般の人に対してどのくらい高度なスキルなのかを伝えることが難しい側面があります。
自身の実績やスキルを専門領域外の人にも理解できるように、平易な言葉で説明することを意識してみましょう。専門領域外の人でも分かる粒度で伝えることで、専門知識を持たない相手にも自分の価値を理解してもらえるようになり、採用に至る確度が高まるかもしれません。
転職活動中は作成した履歴書や職務経歴書を転職エージェントなど転職支援のプロに添削してもらい、分かりやすい内容になっているか確認してもらうことをおすすめします。
転職先候補の企業文化や雰囲気を理解する
スペシャリスト転職を成功させるためには、スキルや専門性の適合性だけでなく、転職先候補に挙がっている企業の文化や雰囲気を理解することも大切です。企業文化や職場の雰囲気が合わない場合、ミスマッチを感じてしまい、早期退職に至る懸念があります。
そのため、転職活動にあたっては、企業のホームページを熟読する、社員面談を設けてもらう、面接の場で質問するなどを通じて、転職先候補に挙がっている企業の文化や雰囲気の理解に努めましょう。
自身の働き方や価値観にフィットする企業を選ぶことで、スペシャリストとして中長期的なキャリアを築いていくことができるでしょう。
求人ポジションにおける業務イメージを擦り合わせる
スペシャリスト転職に向けては、求人ポジションにおける業務イメージを擦り合わせることも重要です。
スペシャリストは特定の分野に長けているからこそ、ちょっとしたミスマッチによって自身の専門性が発揮できなくなるリスクがあります。
転職活動では、求人に記載されている情報だけでなく、実際に任される業務の範囲や成果目標を面接などで確認し、企業と期待値を一致させておきましょう。
周囲と連携しながら成果を出したエピソードも伝える
スペシャリストは高い専門性が求められますが、組織内で成果を創出するためには周囲との連携も不可欠です。転職活動では、採用担当者に「専門性と協調性のバランスが取れた人材」という印象を与えられるよう、専門的なスキルや経験に限らず、他部門やチームと協力して成果を上げたエピソードを交えながら自己PRすることを意識しましょう。
スペシャリストのキャリアプラン
スペシャリストが描くキャリアプランとしては、次のような例が挙げられます。
● 専門性に特化したハイプレイヤー
● 専門性とマネジメントを掛け合わせた管理職
● 管理職でありながら専門性を活かし業務を行うプレイングマネージャー
本章では、上記3種のキャリアプランについて解説します。
専門性に特化したハイプレイヤー
専門性に特化したハイプレイヤーは、特定分野での卓越した知識やスキルを身につけ、実務において高い成果を生み出す役割を担います。具体的には、技術責任者などが挙げられ、日々の技術業務における管理や推進、複雑な問題の解決を主導します。
ハイプレイヤーを目指すには、まず自身の専門領域を明確にしましょう。その上で専門分野の深化を図るための学習や技術習得を継続しつつも、資格取得や論文執筆など、自身の専門性を対外的に証明できる実績を積み重ねることが大切です。
専門性とマネジメントを掛け合わせた管理職
専門性とマネジメントを掛け合わせた管理職も、スペシャリストが描くキャリアプランの1つです。
特定の分野に特化した専門知識を有しながらも、チームの目標設定や業務の進行管理、メンバーの育成を担う管理職としての役割も果たします。
このポジションを目指すには、リーダーシップスキルやコミュニケーション能力を養うことが必須になります。専門的な知識やスキルだけではなく、マネジメントスキルを習得するための研修を受けたり、育成経験を積んだりすることで、専門性とマネジメントスキルを統合したキャリアを形成していくことができるでしょう。
管理職でありながら専門性を活かし業務を行うプレイングマネージャー
プレイングマネージャーは、管理職として組織やチームの統率を行う一方で、自身もプレイヤーとして専門的な業務を遂行するポジションです。例えば、研究職の場合、研究チームの進捗管理を担いつつ、自らも重要な実験や分析に関与するケースが該当します。
プレイングマネージャーになるためには、高度な専門業務を推進できる能力とチームを牽引するマネジメントスキルが不可欠です。また、同時に多様なタスクを処理する柔軟性も必須となるでしょう。
まずは専門的なスキルを磨きながら、管理職として業務全体を俯瞰する力を養うことがポイントです。また、プレイヤーとマネージャーを両立させるための働き方を模索し、自分なりのスタイルを確立することも意識してみましょう。