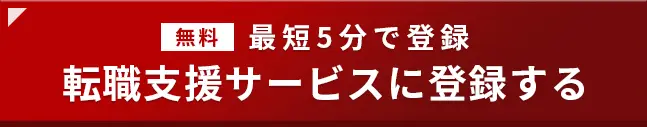転職面接において、面接の終わり際に「最後に一言何かありますか」と聞かれることは少なくありません。しかし、対策をしておかないと何を話すべきかわからず、答えに詰まってしまう方もいることでしょう。
そこで今回は、企業側が「最後に一言」と質問してくる理由や、おすすめの回答例、NGな回答例などをハイクラス転職のJAC Recruitment(以下、JAC)が解説します。ぜひ本記事を参考に、良い印象を与えられる回答を準備してみてください。
転職を検討中ですか?
今現在、
- 自分の市場価値を知りたい
- 今後のキャリアをどうするか整理したい
- 転職活動を無駄なくスムーズに進めたい
上記のようなお困りごとがございましたら、私たちJACへ相談してみませんか?
転職活動の進め方を相談する転職を検討中ですか?
今現在、
- 自分の市場価値を知りたい
- 今後のキャリアをどうするか整理したい
- 転職活動を無駄なくスムーズに進めたい
上記のようなお困りごとがございましたら、私たちJACへ相談してみませんか?
転職活動の進め方を相談する
目次/Index [非表示]
企業側が転職の面接で「最後に一言」と質問する意図
1. 入社の意欲を確かめるため
2. 応募者の人柄を知りたいため
3. もう一押しのアピールチャンスを設けている
企業側は転職の面接において、「最後に一言」という質問を通じて、入社意欲や応募者の人柄を確認しつつ、もう一押しのアピールをさせてくれようとしている場合が多いです。
内定の可能性を高めるためにも、適切に回答し、より良い印象を与えられるようにしましょう。また、そのために企業側の意図を詳しく理解しておくことをお勧めします。
意図1. 入社の意欲を確かめるため
企業側は「最後に一言」の部分で、入社意欲が高いかどうかを確認しています。熱意やモチベーションの高さは面接全体を通じて伝わるものではありますが、最後にこの質問を通じて、「改めて意欲の高さがどの程度かを確認したい」という狙いがあります。
そこで、志望度の高さや企業への貢献意欲を自信を持って表現できれば、面接官に好印象を与えることができます。「自分の言葉」で入社意欲を説明しましょう。また、面接で緊張していたり、伝えきれなかったりした部分があった場合は、最後の機会を生かして、それらの挽回を試みるのも選択肢の一つです。
意図2. 応募者の人柄を知りたいため
「最後に一言」という質問の回答には、応募者の人柄が現れることも多いため「人柄の確認」という意味でも聞かれることが多いです。今後、ともに長く働いていく応募者の人柄が企業に合っているかどうかは、採用にあたって重要な要素の一つです。
人柄が企業に合っている場合は長く働いてくれるでしょうが、もしそうでない場合、早期離職となる可能性もあります。企業は中途採用に時間と費用を大量に投入しているため、早期離職をされては大きな損失となってしまいます。
そのため、自分が企業の社風や雰囲気に合致しており、そして長く働ける人物であることが伝わるような回答ができると理想的です。
意図3. もう一押しのアピールチャンスを設けている
もう一押しのアピールチャンスという意味でも「最後に一言ありますか?」と質問をされることがあります。
面接において、準備してきたことを完璧に、全て話せる応募者は多くありません。緊張してしまったり、話の流れが予想と異なったりして、せっかく用意してきたアピールポイントを話せないまま、面接が終盤まで進むこともあります。このような場合に備えて、もう一度自由に回答できる時間を与えることで、応募者が最後にアピールし損ねた部分がないかを確認しているのです。
従って「せっかく準備してきたのに、聞かれなかった」「うまく答えられなかった」と思っている部分がある場合は、積極的にこの機会を活用してアピールしてみると良いでしょう。
転職面接における「最後に一言」の合否への影響度
結論として、転職面接における「最後の一言」の合否への影響度はそこまで高いものではありません。面接中で判定はほとんど終わっていることが多いため、最後の一言だけで大きく影響することは考えにくいでしょう。
しかし、面接において候補者を採用するかどうかの判断に悩んでいる場合は、この質問が合否を分ける可能性もあります。
人は一般的に、最後に聞いた内容や印象が記憶に強く残る傾向があるため、締めくくりにおいてポジティブで力強いメッセージを伝えれば、良い印象を与え、最終的な評価が大きくプラスに働くこともあります。
転職面接の「最後に一言」の回答方法と例文
1. 入社意欲の高さや熱意をアピールする
2. 自己PRの補足をする
3. 逆質問をする
4. 面接の感謝(お礼)を伝える
続いて、「最後に一言」と聞かれた際の回答方法と例文を紹介します。
「入社意欲の高さや熱意をアピールする」「自己PRの補足をする」「逆質問をする」「面接の感謝を述べる」の4つに分けて解説します。ポイントとともに参考にしてみてください。
回答例1. 入社意欲の高さや熱意をアピールする
回答例:
「面接を通じて、さらに御社への入社意欲が高まりました。
公式サイトを拝見するなど、御社に関する情報収集をさせていただき、やりがいを感じられる環境であるとは存じ上げておりましたが、〇〇様(面接官 or 面接に同席した現場の方)のような方と働ける可能性があると思うと、より身が引き締まる思いです。
御社に入社できた暁には、前職の営業経験で身に付けた傾聴力を生かし、クライアント企業の問題を詳細まで分析し、解決に導けるコンサルタントとして活躍を目指します。」
回答のポイント:
入社意欲の高さが伝わると、企業は「この人は長く働いてくれる」と信頼してくれます。企業研究をしっかり行っていたことを再度強調しつつ、面接でさらにモチベーションが高まったことを伝えると、信憑性も高まるでしょう。
回答例2. 自己PRの補足をする
回答例:
「先ほど、私の長所はプログラミングスキルであるとお話ししましたが、同様にリーダーシップにも自信があります。
前職では主にプログラマーとして働いていましたが、プロジェクトマネージャーを務めるエンジニアとも密に連絡を取っており、マネージャー不在時にはプロジェクトを統括する役割を担っていました。
従って、一旦はプログラマーとしての入社を目指しますが、将来的には大規模な制作プロジェクトをまとめる人物として、リーダーシップも発揮したいと考えています。」
回答のポイント:
自己PRの場面で満足にアピールできなかった場合や、他にも自信のある能力を持っている場合は、自己PRの補足をしても良いでしょう。求められている人物像に沿っていて、自己PRでアピールした能力と掛け合わせるとさらに活躍が期待できるような能力だと、より理想的です。
回答例3. 逆質問をする
回答例:
「御社ではプロジェクト形式で業務が進むことが多く、それぞれのメンバーとの綿密なやり取りが欠かせないため、コミュニケーション能力が重要であると伺いました。
そして、コミュニケーション能力に自信があることも先ほどご紹介させていただきましたが、その他に求められる能力は何があるでしょうか。
もし内定をいただけた場合、入社までの期間は長くありませんが、少しでもその能力を磨き、御社に貢献したいと考えています。現段階で〇〇様(面接官)が思いつくものがあればご教示いただけますと幸いです。」
回答のポイント:
まず、企業研究をしっかり行っていることを簡潔に伝えた後に、他に必要な能力について聞いています。
逆質問をするということは、企業に深い関心があるということです。さらに必要な能力について聞き、それを入社までに身に付けようとしているということは、非常に意欲が高いと判断してもらえます。
回答例4. 面接の感謝(お礼)を伝える
回答例:
「本日は、このような貴重な機会をいただき、誠にありがとうございました。面接を通じて、御社で働きたいという意欲がさらに高まりました。
また、〇〇様(面接官)のような方とともに仕事ができると考えると、少しでも貢献するために努力を重ねようという気持ちが高まっています。
もし内定をいただけた際には、全力で御社に貢献できるよう取り組みますので、よろしくお願いいたします。」
回答のポイント:
特に聞きたいことや言いたいことが思いつかない場合や、逆質問をしようとしていた項目が面接中に解決されてしまった場合、無難に感謝を述べるのも選択肢の一つです。
誠実さや意欲が伝わる感謝を述べる応募者に対して悪いイメージを持つ面接官はいません。また、逆質問が面接の途中で解決してしまった場合「実は〇〇についてお伺いしようと思っていたのですが、先ほどお伝えいただいたので」と添えてからお礼を伝えても良いでしょう。
転職面接の「最後に一言」回答NG例
1. 「特にありません」と回答
2. 話が長くなりすぎてしまう
3. 休暇・残業など労働条件に関する質問
4. 同じ内容の回答を繰り返す
続いて、転職面接における「最後に一言」のNG例について紹介します。以下のような回答をしてしまうと、意欲が無い人物であると判断され、非常にマイナスな印象を与えてしまう可能性が高いため、注意が必要です。
NG例1.「特にありません」と回答
「最後に一言」の場面で「特にありません」という回答はあまり望ましくありません。「意欲がない」「準備不足である」と思われてしまう可能性が非常に高い回答といえます。
面接官は「最後に一言」という質問を通じて、応募者の意欲や人柄を確認しつつ、最後にアピールの機会を与えています。そのため、最後の機会を生かそうとしないということは「やる気がない」と捉えられても仕方ありません。「最後に一言」の質問は面接の結果を大きく左右するものではありませんが、この回答をした場合、印象が非常に良かったとしても、不採用に近づく可能性が高まるといえるでしょう。
もちろん、用意してきた質問が面接中に解決されてしまうことや、忘れてしまうことがあるかもしれません。このような場合は「特にありません」と回答するのではなく、疑問が解決してしまった旨を伝え、忘れてしまった場合も面接の感謝を述べるだけでも十分です。
「何も言わない」のではなく、せめて何か一言述べて、面接を締めくくるようにしましょう。
NG例2. 話が長くなりすぎてしまう
話が長くなりすぎてしまうのも、避けるべき行動の一つです。最後に「一言」と言われているため、あまりにも長いと質問の趣旨から逸れる上に「レギュレーションを守れない人物である」と思われてしまいます。基本的には回答は1分以内に収めるのが良いとされているため、目安として覚えておくことを推奨します。
ただし、あまりにも短すぎる一言だけで終わらせてしまう、例えば「ありがとうございました」と言うだけだと印象が悪くなり、モチベーションの高さを疑われてしまう可能性もあるため、ある程度中身があることを話すように心掛けてください。
NG例3. 休暇・残業など労働条件に関する質問
休暇や残業など労働条件に関する質問は、業務内容とは離れた事柄であるため「入社意欲が低いのではないか」と判断されてしまいます。特に、このような条件は調べればわかる場合がほとんどであるため、貴重な面接の時間を割いて聞くようなことではありません。
「面接の最後の場面」という貴重な時間を使ってでも休暇や残業などについて聞いてくるということは、リサーチが足りないだけでなく「休みや給料だけにしか興味がない人物」と思われてしまう可能性も考えられます。
企業は、業務に対してモチベーションを高く保ち、やりがいを持って取り組んでくれる人物を求めています。休暇・残業など労働条件ばかりに言及するような人は、採用したくないと考えている担当者もいるでしょう。
NG例4. 同じ内容の回答を繰り返す
面接中に出た話題を補足するのは問題ありませんが、全く同じ内容の回答を繰り返すことだけは避けましょう。「最後に一言」で自己PRをすることは構いませんが、面接中に話した自己PRと同じ話をしても意味がありません。
従って、別の話題を取り上げるか、もし自分の話したいことが十分に伝わっていない可能性があると判断し、同じことを話したいと感じた場合は「繰り返しになりますが」など「クッション言葉」を用いるようにしましょう。
転職面接の対策は「JAC」へお任せください
この記事では、転職面接において「最後に一言何かありますか」と聞かれた際の企業側の意図や、良い回答例と悪い回答例を紹介しました。
この質問は「合否を左右する非常に重要な質問」と言えるほどではないものの、当落線上にある場合は選考に影響を与える可能性があります。また、準備しておかないとうまく回答できない可能性が高い質問であるため、入念な対策が欠かせません。
転職エージェントの「JAC」では、求人紹介はもちろんのこと、面接対策のお手伝いも行っています。
「どのような回答をすれば企業側に響くか」という観点での面接練習のサポートも可能です。転職面接の練習を徹底的に行い、自信を持って本番に臨みたい方は、ぜひ一度JACのコンサルタントにご相談ください。