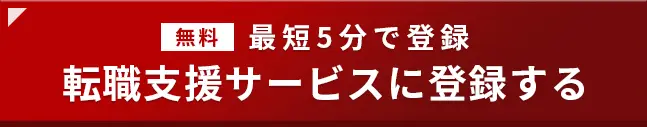「転職するのに最適な時期はいつだろうか?」「賞与や社会保険で損にならない転職時期を選びたい」
転職を成功させるために、少しでも有利になる時期や、おすすめの時期を知りたいと思うときがあります。しかし、転職に適した時期や、自分にとって最適なタイミングをどのように見極めればよいのか、具体的な方法はわかりにくいものです。
この記事では、転職に有利な6つの時期の特徴、自分に合った最適な転職時期を決めるポイント、転職を避けた方がよい時期についてハイクラス転職のJAC Recruitment (以下、JAC)が解説します。
転職を検討中ですか?
今現在、
- 自分の市場価値を知りたい
- 今後のキャリアをどうするか整理したい
- 転職活動を無駄なくスムーズに進めたい
上記のようなお困りごとがございましたら、私たちJACへ相談してみませんか?
転職活動の進め方を相談する転職を検討中ですか?
今現在、
- 自分の市場価値を知りたい
- 今後のキャリアをどうするか整理したい
- 転職活動を無駄なくスムーズに進めたい
上記のようなお困りごとがございましたら、私たちJACへ相談してみませんか?
転職活動の進め方を相談する
目次/Index [非表示]
- 1 転職が有利な時期・おすすめ時期はある?特徴別に6つの時期をご紹介
- 2 1. 転職の求人が増える時期:1~3月や7~9月
- 3 2. 転職で狙い目の穴場時期: 転職活動者が減少する4~5月や12月
- 4 3. 転職の時期:賞与(ボーナス)支給後に転職できるタイミングは?
- 5 4. 転職の時期:転職するなら何月がいい?社会保険・税金手続きが楽な時期
- 6 5. 転職の時期:在職中でも転職活動の準備に時間をかけやすいのは何月?
- 7 6. 転職しない方がいい時期:タイミングが悪い時期の例
- 8 自分にとって最適な転職時期を決める5つのポイント
- 9 転職時期に関するFAQ
- 10 ハイクラス転職のJACは転職時期のご相談にも対応
転職が有利な時期・おすすめ時期はある?特徴別に6つの時期をご紹介
転職のおすすめ時期は人によって異なります。また、求人が多い中で選びたいのか、それともニッチな職種の求人が出る時期を狙いたいのかによっても、有利になる時期は違ってきます。結論からお伝えすると、転職にベストな時期は、転職や退職をしたいと思ったタイミングに合わせた時期になります。自身の退職目標予定に合わせて、自分自身のタイミングが良いときに活動を開始することで、満足度の高い転職につながりやすいでしょう。
ただし、求人市場には季節変動があります。企業の採用ニーズが高まる時期もあり、これらの動向を把握しておくと、より戦略的に転職活動を進めやすいでしょう。
この先の章では、転職の求人が多い時期、そうでない時期などを、特徴を7つに分けて詳しく解説します。
1. 転職の求人が増える時期:1~3月や7~9月
【転職の求人が増える時期】
1~3月(春入社向けに求人が増加)
・入社予定を4月など春に設定して採用活動を行う企業が多い
・3月末退職者の補充の求人も多い
・新卒と入社のタイミングを合わせるために中途採用に動き出す傾向がある
・年度切り替えの新規事業立ち上げ求人も期待できる
7~9月(下半期スタート向けが増加)
・ボーナスを受け取って転職活動する人も多い
・即戦力となる人材を求める傾向が強い
・専門性の高い求人・重要ポストの補充も多い
・通常では見られない求人情報の公開も期待できる
・下半期始動に向けて受け入れ体制が整っている
転職の求人が増える時期は、4月などの春入社予定の1~3月、下半期開始に向けての7~9月です。
どちらも法人の決算月にそった上半期、下半期といった新年度、半期の組織再編時期に合わせて人員を確保したい意図から求人数が増えます。求人数が増える分、転職希望者も増加するため、ライバルが多く、内定を得るためのハードルが高くなりやすい傾向にあります。よりしっかりとした転職準備が必要です。
求人が最も多い春入社に向けて1~3月に転職活動
【1~3月の転職活動のメリット・デメリット】
メリット
・幅広い職種・部門の求人が増加するため選択肢が多い
・研修が充実し、職場にもなじみやすい
・冬のボーナスを受け取れる
デメリット
・ライバルが多く、選考には十分な準備が必要
・複数社を受けても内定が同時期でない可能性が高い
1~3月は、4月からの新年度に向けた体制整備のため、中途採用市場が非常に活発化する時期です。幅広い職種・部門での求人が増加し、未経験者対象の求人も多くなります。また、3月の退職者を補充する求人も見られます。
この時期の転職活動のメリットは、求人が増えるため選択肢が広がることです。4月など春からの入社を目指す場合、新卒と合わせた入社研修が実施されることが多く、手厚い社内教育を受けやすい点も魅力です。また、同時期に中途入社する人が多いため、職場に馴染みやすいです。冬のボーナスを受け取ってから転職活動を始められるのも利点です。
一方、デメリットとしては、転職希望者が多いため、人気のある企業やポジションでは選考が厳しくなりがちです。年末年始休暇を利用して早めに準備することがおすすめです。さらに、企業によって選考スピードが異なるため、内定時期がばらつくこともあります。そのため、複数の内定を比較検討するのが難しい場合があります。自身の優先順位をしっかりと決めた上で、応募や選考スケジュールを立てることが重要です。
下半期スタートに合わせた秋入社|7~9月に転職活動
【7~9月の転職活動のメリット・デメリット】
メリット
・下半期スタートにあわせて即戦力を求める求人が多い
・普段見られないポジションなどが出ることもある
・受け入れ体制・研修が充実し、職場にもなじみやすい
デメリット
・ライバルが多く、選考には十分な準備が必要
・8月9月は休暇も多いため日程管理が重要になる
7~9月は、10月からの下半期始動に向けて組織再編や新たな事業計画を見据えた求人が増加します。
そのためこの時期は、新体制で即戦力となる方を求める求人が多いです。また、新体制稼働に不足しているポジションを埋める単発求人が見られる場合もあります。この時期は受け入れ体制が整っているため、中途入社向けの研修が充実していることも利点です。
デメリットとしては、夏のボーナス後の転職活動が多く、選考通過が難しくなることがあります。特に即戦力採用が重視されるため、ポジションが限られ、選考準備をより入念に行う必要があります。また、企業の夏季休暇や現職での休暇が重なりやすいため、面接日程や引継ぎが難しくなることもあります。したがって、早めの準備が重要です。
2. 転職で狙い目の穴場時期: 転職活動者が減少する4~5月や12月
転職で狙い目の時期は、転職活動者が少なくなる4~5月、12月などです。どちらも転職活動をする人が比較的少ないため、ライバルが減って、転職活動がしやすくなります。
転職時期の穴場|4~5月・12月は転職活動者が少なめ
【転職時期の穴場:転職活動のメリット・デメリット】
メリット
・欠員補充のため、急遽即戦力を求める求人が多い
・ライバルが少ない
・採用活動が混んでないため、うまくいけば選考が進みやすい
デメリット
・求人数が少ないため、希望する求人があるとは限らない
・現職でのボーナスを受け取れない
・4~5月は現職も忙しく、転職活動しにくい場合も多い
・12月は年末年始休暇で採用プロセスが遅くなりやすい場合もある
4~5月は新入社員の退職や、既存社員の異動による人員不足を補うための求人が増える時期です。またそういった事情から、急募の求人が多く、選考が迅速に進むことが多いです。
この時期の転職活動のメリットは、転職活動をする人も少ないためライバルが控えめで、比較的落ち着いて活動ができることでしょう。デメリットとしては、求人数の減少で選択肢が少ないことや、欠員補充の求人が多いため、希望する業界や職種が見つからない点が挙げられるでしょう。また、在職中の場合、4~5月は新年度の業務が忙しく転職活動に時間を割きにくいことがネックになるかもしれません。
12月は、ボーナスをもらってから退職する人のポジションが空くことがあるため、通年採用が行われていないような求人が出やすくなるのも魅力です。早い企業では4月などの春入社求人が出る場合もあるため、12月初旬に応募することで、年末年始の休暇を利用して転職準備を進められるという利点もあります。一方でデメリットとしては、年末に採用活動を控える企業が多く、求人数がほかの月に比べて少ないことが挙げられます。また、年末年始の休暇で採用担当者や決裁者が不在になりやすく、選考プロセスが遅れる可能性も高いです。
4~5月や12月は求人数が少ない時期ですが、同時にライバルも少ないため、もし自分に合った求人が見つかれば、事前に準備を整えておくことで、採用のチャンスが広がるでしょう。
3. 転職の時期:賞与(ボーナス)支給後に転職できるタイミングは?
【賞与(ボーナス)をもらってからの転職目安】
・現職に配慮しながら辞める方法
⇒賞与支給後から数週間で退職を申し出る
・転職活動にかかる期間:1~3ヵ月
・退職目安時期:6月賞与⇒7~9月、12月賞与⇒1~3月
・転職活動目安:4~6月・10~12月
転職する際に賞与(ボーナス)をもらってから退職したいと考える方もいるでしょう。
一般的に賞与が支給される6月・12月にボーナスを受け取ってから転職する場合、4~6月、10~12月に転職活動を始めるのが目安です。確実に賞与をもらって辞めるには、賞与の支給後、数週間経過してから退職を申し出ると、気まずさを軽減できることが多いようです。退職までには通常1~3ヵ月かかるため、逆算して退職時期の目安は7~9月、1~3月となります。転職活動に3ヵ月かける場合、活動は4~6月、10~12月に始めるのが理想です。
ただし、ボーナス支給の要件は会社ごとに異なるため、事前に就業規則で確認することが重要です。一般的には「支給日在籍要件」に基づき、ボーナス支給日に在籍している従業員にボーナスが支給されます。場合によっては、賞与が「支給日の前月末に在籍していた従業員に支給」されることもあります。このようなケースでは、支給時に在籍していなくても賞与を受け取れることになるでしょう。
現在、具体的な支給基準が就業規則等にない場合、従業員の賞与請求権は認められないとされています。そのため、会社の規定を確認してから、退職時期や転職活動のタイミングを決めることが大切です。
4. 転職の時期:転職するなら何月がいい?社会保険・税金手続きが楽な時期
【社会保険の手続きが楽な退職時期】
・社会保険の資格喪失日は退職日の翌日
・退職後すぐに別の会社に再就職する場合
・一番楽なパターン:末日退職で翌月1日入社
(自分で手続き不要)
【年金切り替えの手続きが楽な退職時期】
・厚生年金保険の資格喪失日は退職日の翌日
・退職後すぐに別の会社に再就職する場合
・一番楽なパターン:末日退職で翌月1日入社
(自分で手続き不要)
【所得税・住民税の手続き】
・1~10月の退職で同年内に転職の場合
⇒転職先の企業で手続きしてくれる
・11月と12月の退職の場合
⇒自分で確定申告の必要があるため注意
転職する際に社会保険や税金の手続きを簡単にしたい場合、前職の退職日と転職先の入社日が重要です。手間を最小限に抑える最も楽なパターンは、退職日を月末、入社日を翌月1日にしましょう。
以下で詳しく説明します。
社会保険で損をしない退職日と転職先の入社日
社会保険では、資格喪失が退職日の翌日となるため、手続きが最も簡単になるのは、退職日を月末、入社日を翌月1日にする場合です。この組み合わせでは離職期間がないため、自分で手続きをする手間が省け、余計な社会保険料の支払いも避けられます。そのため、可能であればこのパターンを目指すのがおすすめです。
退職日と入社日が同じ月内の場合(例: 退職が7/10で入社が7/15など)は、離職期間中の社会保険の変更手続きが必要ですが、社会保険料は転職先が処理するため大きな負担はありません。社会保険で損をするのは、退職日と入社日が月をまたぎ、かつ離職期間がある場合(例: 退職が7/10で入社が8/5など)です。この場合、7/11~7/31の社会保険料を自己負担し、会社が負担していた分も全額負担する必要があります。そのため、できるだけ退職日を末日、入社日を翌月1日に設定するように調整することが重要です。
厚生年金保険で損をしない退職日と転職先の入社日
厚生年金保険の資格喪失も退職日の翌日となるため、手間がかからず損をしないためには、退職日を月末、入社日を翌月1日にするのが最適です。
離職期間ができた場合、家族の厚生年金の扶養に入るか、国民年金に加入する必要があります。家族の扶養に入れれば社会保険料は変わりませんが、一時的に国民年金に加入すると金額が厚生年金保険よりも高くなることがあります。そのため、厚生年金保険での支出を抑えるためには、やはり退職日を月末、入社日を翌月1日にするように調整するとよいでしょう。
税金(所得税・住民税)の手続きが楽になる退職の時期
税金(所得税・住民税)の場合、会社に所属していると11月・12月に年末調整が行われます。そのため、1月~10月に退職して年内に再就職する場合は、転職先で年末調整の手続きを行ってくれるため、手間がかかりません。
税金で注意が必要なのは、11月・12月に退職する場合です。この時期に退職すると、転職先での年末調整に間に合わないため、自分で前職の源泉徴収票をもとに確定申告をする必要があります。確定申告をしても税金が増えるわけではありませんが、手間がかかります。住民税の計算については、年内に転職する場合、前職で退職時に一括納付すれば、余計な手間を省くことができるため心配はいらないでしょう。
5. 転職の時期:在職中でも転職活動の準備に時間をかけやすいのは何月?
【在職中でも転職活動の準備に時間がかけやすい時期】
・5月・・・ゴールデンウィークを利用
・8月・・・お盆休みを利用
・12月・・・年末年始休暇を利用
在職中で業務が忙しいと、転職活動のための時間を確保するのも難しい場合があります。準備不足だと選考が進まず、転職活動が長引きやすくなります。
そのような時は、長期休暇を利用して自己分析や企業研究、職務経歴書の作成、面接の準備を行うとよいでしょう。まとまった時間で集中して準備を進めることで、選考に通過しやすくなります。
6. 転職しない方がいい時期:タイミングが悪い時期の例
中途採用は基本的に年間を通して行われているため、転職しない方がいい時期やタイミングの悪い時期は特にありません。求人数が少ない時期でもライバルが少なく、チャンスと捉えられます。
ただし、転職を避けた方がよい時期として、以下の2つのケースがあります。
1つ目は、勤務先の繁忙期や自身が関わる大きなプロジェクトの途中の時期です。このような時期に退職すると、チームや会社に負担をかけ、将来的な評判にも影響する可能性があります。また、重要な経験や成果を逃す恐れもあります。転職を考える際は、現在の責任が全うできる時期を選ぶことが大切です。
2つ目は、重要なライフイベントの前後です。結婚・出産・住宅購入など、生活に大きな変化をもたらす出来事の前後は、心身ともに不安定になりやすく、冷静な判断が難しくなります。新しい環境への適応とライフイベントへの対応を同時に行うのは、過度なストレスを招く恐れがあります。
転職のタイミングを選ぶ際は、これらの時期を避け、自身のキャリアと生活の安定を考慮することが重要です。
自分にとって最適な転職時期を決める5つのポイント
【最適な転職時期を決める5つのポイント】
1. 現職場にきたす支障がなるべく少なく済むタイミング
2. 自分のライフイベントへの支障をなくす
3. ボーナス・社会保険の影響を考え退職は月末で想定
4. 最新の転職市場の動向を見極める
5. 転職のプロに具体的なタイミングを相談する
転職の最適な時期は個人によって異なります。
しかし、以下の5つのポイントを考慮することで、自分にとって最適なタイミングを見極めやすくなるでしょう。具体的なポイントを簡単にみておきます。
ポイント1. 現職場にきたす支障がなるべく少なく済むタイミングを選ぶ
転職の時期を選ぶ際は、プロジェクトの途中や繁忙期を避け、円滑な引き継ぎがしやすい時期を選びましょう。
退職すると決めていても、同僚や上司に迷惑をかけないように配慮することで、転職後にも良好な関係を維持しやすくなります。また、自身の業務を適切に締めくくることで、次のキャリアへの良いスタートが切れます。退職時期を慎重に検討し、会社と相談しながら決定するようにすると円満退職もしやすいでしょう。
ポイント2. 自分のライフイベントへの支障をなくす
転職を検討する際は、結婚・出産・子育て・引っ越し・子の進学・親の介護など、個人的な重要イベントと転職のタイミングが重ならないように調整しましょう。
新しい環境に適応するには時間が必要であるため、ライフイベントと重ならないよう計画することで、双方のバランスが保ちやすくなり、ストレスがたまることも避けられます。転職活動を始める前に、今後の予定を把握し、どのタイミングで新しい仕事をスタートするのが最適かを見極めるようにしましょう。
ポイント3. ボーナス・社会保険の影響を考えて退職は月末で想定する
先にもご紹介しましたが、ボーナスを受け取って退職したい場合は退職日の目安を決めてから、転職活動を始めるとよいでしょう。
ボーナスを受け取っておくことで、経済的な不安が減少するため、可能であれば、ぜひ就業規則を確認して、退職日を計画してください。社会保険への切り替えは、退職日を月末、入社日を翌月1日にすることで、損をせずにスムーズに転職先へ移行できます。
こちらも可能であれば、念頭に入れて調整しておくとよいでしょう。転職後の手間や不安の軽減につながります。
ポイント4. 最新の転職市場動向を見極める
転職市場の動向は経済情勢や業界特有の出来事の影響によって変わりやすいです。そのため、転職の時期を考える際は、希望業界・職種の、最新の転職市場動向・給与水準・求人数などを綿密にチェックすることが大切です。わずかなタイミングの違いで求人の質が大きく変わることもあります。高度な専門性が求められる職種や管理職クラスの求人は、欠員が生じた際にチャンスとなることが多いです。
転職を考えている間は情報収集を怠らず、注意深く最新の市場情報や業界ニュース、求人サイトをチェックするようにしておきましょう。
ポイント5. 転職のプロに具体的なタイミングを相談する
転職の時期が決めきれない場合は、転職のプロに具体的なタイミングを相談するとよいでしょう。転職エージェントは、業界別に最新の転職動向、成長率、求人傾向などを常に分析して把握しています。
また、多くの転職成功事例や企業とのネットワークを持っているため、個々の転職希望者にあった最適な時期やタイミングのアドバイスを提供できます。一人ひとり、最適な転職のタイミングが違うからこそ、ぜひ自身にあった時期、転職の進め方について相談してみてください。プロの知見を活用することが、転職成功の近道にもなります。
転職時期に関するFAQ
こちらでは、転職時期に関するFAQをご紹介します。
Q1. 転職活動を始める理想的な時期は何カ月前でしょうか?
転職活動を始める理想的な時期は、早ければ退職希望日の6ヵ月前、遅くとも3ヵ月前に始めるのがよいでしょう。
また、転職活動にかかる期間の平均は約2ヵ月です。厚生労働省の調査結果によれば、転職活動を始めて退職するまでの期間で、全世代で最も多いのが1ヵ月~3ヵ月未満で、次に多いのが1ヵ月未満という結果が得られています。そのため、3ヵ月より前に、自身の動きやすいタイミングでスタートするとよいでしょう。
Q2. 転職する際、辞表提出はいつごろが目安になりますか?
多くの企業では、退職日の1~3ヵ月前に辞表を提出することが推奨されています。早めに伝えることで、引継ぎや後任者の採用もスムーズに進みやすくなります。法律上では退職日の2週間前までに辞表を提出すれば退職が可能です。
そのため、転職先が決まった後、退職日の1~3ヵ月ほど前に、直属の上司に面談を申し入れて、退職の旨を伝えるようにしましょう。
Q3. 転職エージェントに相談する時期はいつがよいでしょうか?
転職エージェントに相談する時期は、転職をまだ決めていない段階から、いつでも相談しても大丈夫です。ただ、あえて時期でいうなら、転職を決めている場合は転職希望日の3~6ヵ月前がよいでしょう。もし、キャリアプランから相談したい場合は、早めに相談することで、プランを立ててから求人紹介にうつることができます。
また、競争が激化する前に有利に進めたい場合は、転職市場が活発になる前の時期(1~3月・7~9月)より前に相談することで、早めに準備を進められやすくなります。
ハイクラス転職のJACは転職時期のご相談にも対応
ハイクラス転職のJACは、専門の転職コンサルタントが転職時期のご相談にも対応いたします。
管理職・エグゼクティブ・専門職の転職支援に特化
JACは、管理職やエグゼクティブ、専門職といったスペシャリストの領域に特化した転職支援サービスです。
また、海外に拠点があることから、インターナショナルな領域で活躍する人材の転職支援も得意としています。
業界・職種に精通した転職のプロフェッショナルがサポート
JACには各業界や職種に特化した約1,400名のコンサルタントが所属しており、その一人ひとりが高い専門性を備えて転職希望者の転職をサポートしています。
コンサルタントは日頃から企業に直接訪問しているため、企業の文化や風土、事業戦略までも把握したうえで、他では得られないリアルな情報を転職希望者へ知らせることも可能です。
「コンサルタント型」ならではの質の高いサービスを提供
JACでは、企業と転職希望者の双方をコンサルタントが担当する「コンサルタント型」を導入しています。そのため、JACのコンサルタントは単に求人を紹介しているだけでなく、企業の採用ニーズの動向や中長期的なキャリア形成も視野に入れ、転職希望者様一人ひとりに合ったキャリアプランの提案が可能です。
自身にとっての転職の最適な時期を決めかねている、そのような場合はぜひお気軽にJACにご相談ください。