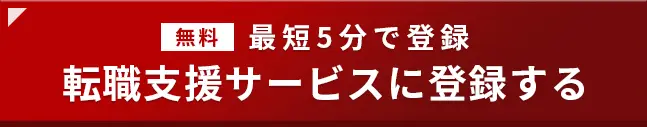転職活動を成功させるためには、1社だけでなく、複数の企業に応募して、リスクを分散させつつ取り組むことが一般的です。しかし、応募を増やしすぎると、一つ一つの企業対策を十分に行えません。
転職を成功させるためには「自分が納得できるレベルまで入念な対策ができる最大数の応募」を行うと良いでしょう。また、複数社を並行して転職活動を進める場合、いくつかの注意点や、転職の応募数を絞るべきケースも存在します。
そこでこちらでは「転職で複数社に応募すべき理由」「複数社を並行して転職活動を進める場合の注意点」「転職の応募数を絞るべきケース」の3つについて、ハイクラス転職のJAC Recruitment(以下、JAC)が解説していきます。転職活動を進めるにあたり、何社程度応募するかを検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
転職を検討中ですか?
今現在、
- 自分の市場価値を知りたい
- 今後のキャリアをどうするか整理したい
- 転職活動を無駄なくスムーズに進めたい
上記のようなお困りごとがございましたら、私たちJACへ相談してみませんか?
転職活動の進め方を相談する転職を検討中ですか?
今現在、
- 自分の市場価値を知りたい
- 今後のキャリアをどうするか整理したい
- 転職活動を無駄なくスムーズに進めたい
上記のようなお困りごとがございましたら、私たちJACへ相談してみませんか?
転職活動の進め方を相談する
目次/Index [非表示]
転職活動では何社応募すべきか
- 応募数の目安は5~10社
- 注力して取り組める範囲の応募数を推奨
- 転職活動の進捗に応じて応募数は調整する
転職活動において、基本的な応募数の目安は5~10社程度とされています。しかし、これはあくまで目安であり、基本的には転職に注力して取り組める応募数にすることを推奨します。また、転職活動の進捗に応じて、応募数を臨機応変に調整するようにしましょう。
応募数の目安は5~10社
転職活動において、応募する企業の数は人によって差があり、目指す業界や職種によっても異なります。一般的には5社から10社を目安に応募することが推奨されていますが、これはあくまで「目安」であり、必ずしも全ての人に当てはまるわけではありません。また、仕事をしながら転職活動をしている場合、応募数は少なめにした方がスムーズに転職活動を進められるでしょう。
しかし、残業が少なく、退勤後や休みの日は転職活動に専念できるならば、ある程度応募数を多めにしても問題ありません。「5~10社」を目安にしつつ、適宜調整してください。
注力して取り組める範囲の応募数を推奨
応募する企業数を決める際には、むやみに数を増やすのではなく、1社1社に対してしっかりと情報収集を行い、適切な準備ができる範囲で応募することを推奨します。
内定を得るためには、応募先の企業について深く理解し、その企業の求める人物像や文化に自分が合っているかどうかを見極めることが欠かせません。特に、志望動機や面接対策は全ての企業に共通した対策があるわけではなく、その企業に特化した対策が求められるため、あまりに多くの企業に応募しすぎると、準備が不十分になってしまいます。
そのため、応募する企業の数は自分がしっかりと取り組める範囲内に絞り、各企業に対して質の高い応募書類と面接の準備ができるように心掛けましょう。
転職活動の進捗に応じて応募数は調整する
転職活動を進める際は、最初から「〇社に応募する」と決めつけるのではなく、選考の状況に応じて応募数を調整することを推奨します。最初の数社で選考が進んでいる場合、新しく応募するのではなく、現在進行している選考に注力した方が良いかもしれません。
逆に、エントリーシートや一次面接の段階でなかなか通過できない場合は、さらに応募数を増やすことも選択肢の1つです。
転職活動は「これだけの時間をかければ必ず成功する」「この工夫をすれば必ず内定が得られる」といった確定的な要素があるわけではないため、計画どおりに進むものではありません。そのため、進捗状況を常に見極め、応募数を臨機応変に調整することが成功の鍵となります。戦略的に転職活動を進め、納得いく形で終わらせられるようにしましょう。
転職で複数社を応募すべき理由
- 並行して選考を進めることで転職活動期間を短くできる
- 転職先の選択肢が広がる
- 条件を比較しやすい
転職においては、基本的に1社だけに絞るのではなく、複数社に応募することを推奨します。なぜならば、並行して応募を進めることで、転職活動の期間を短くでき、転職先の選択肢も広がるためです。
また、複数社に応募することで、条件が比較しやすくなり、自分に最適な企業がどこなのかを検討しやすくもなります。
理由1. 並行して選考を進めることで転職活動期間を短くできる
複数の企業に同時に応募する最大のメリットは、転職活動の期間を短縮できることです。1社ずつ結果を待ってから次の求人に応募していると、不採用が続いた場合、また一から応募先を探すことになり、転職活動が長引いてしまいます。
特に書類選考や面接の間には一定の期間があるため、1社ずつ進めていると、その間に無駄な時間が発生します。そこで、複数社に並行して応募することで、効率的に転職活動を進めることができるのです。
転職活動全体にかかる期間は3ヵ月から6ヵ月程度が目安とされていますが、並行して複数社の選考を進めれば、より早く転職を終わらせることが可能です。また、志望度の高い企業から不採用の通知が届いても、他の選考が進んでいれば精神的な負担が軽減されるというメリットもあります。
理由2. 転職先の選択肢が広がる
複数社に応募するということは、転職先の選択肢が広がるということでもあります。複数の企業に応募する過程で、新しい選択肢を見つけられるかもしれません。
当初はある業界や職種にしか興味がなかったとしても、求人を探す中で、今まで検討していなかった業界や職種に興味を覚える可能性があります。新しい発見があれば、自分のキャリアをさらに広げるきっかけとなり、より多様なキャリアパスを選択できるようにもなります。また、複数社に応募することで、選考過程で得たフィードバックや面接経験を生かして、自己PRや志望動機の内容をブラッシュアップすることも可能です。
以上のことから、複数社に応募することで転職先の選択肢が広がるのはもちろん、それぞれの応募書類や面接の質を向上させることにもつながるといえるでしょう。
理由3.条件を比較しやすい
複数社に応募すると、条件をそれぞれ比較しやすくなります。給与や休日、福利厚生といった条件は応募する前から比較できるかもしれませんが、より細かい雰囲気や社風、業務内容などといった部分は、選考を通過するにつれて理解できる部分もあります。
選考に進む段階で「なんとなく想像と違う」と感じることもありますし、反対に、志望度が低かったとしても、いざ選考を受けてみると雰囲気が非常に良く「この企業に入りたい」と思うこともあります。条件を比較した結果、志望順位が入れ替わることもあるでしょう。転職活動は「企業の採用担当者に選んでもらうこと」が目的ですが、「面接官の方が偉い」というわけではありません。
転職希望者も「選ぶ立場」にあるため、企業を1つだけに絞って受けるのではなく、複数の企業に応募し、それぞれの条件を比較検討することを推奨します。
複数社を並行して転職活動を進める場合の注意点
- 転職では内定通知後に保留できる期間は短い
- 数を増やしすぎて一つ一つの対策がおろそかにならないように
複数社を並行して転職活動を進める場合の注意点も紹介します。
まず、新卒の時と比べて、内定通知後に保留できる期間が短いということを覚えておいてください。また、数を増やしすぎて、一つ一つの対策がおろそかにならないよう注意しましょう。
注意点1. 転職では内定通知後に保留できる期間は短い
新卒の場合、内定通知をもらった後に保留にできる期間が長く、落ち着いて他の企業の選考を受けることができますが、転職の際は一般的に1週間程度と非常に短いです。この期間内に他社の選考結果を待たなければならない場合、スケジュールの調整が重要になります。
もし複数の企業から内定をもらえそうな状況にあるならば、各企業の最終選考のタイミングを慎重に調整しなければなりません。優先度の高い企業の選考を前倒しする、または他の企業の選考を少し遅らせるなどの工夫が求められます。また、内定をもらった企業に対して正直に状況を説明し、回答の猶予をお願いすることも選択肢の1つです。
ただし、保留期間が長引くと企業側にマイナスの印象を与えかねないため、早めに決断できるよう、計画を事前に立てることを推奨します。
最悪の場合「複数の内定をもらえたにもかかわらず、調整がうまくいかず、希望する企業を選べない」という事態に陥るため、スケジュール管理が重要となります。
注意点2. 数を増やしすぎて一つ一つの対策がおろそかにならないように
先に述べたとおり、複数社に同時に応募することでリスク回避は可能であり、スムーズに転職活動を進めることもできます。しかし、一つ一つの企業に対しての対策がおろそかになってしまうと、本末転倒です。
転職活動においては、志望動機や面接対策はそれぞれの企業に合わせたオーダーメイドのものを作成するべきです。企業研究や志望動機の作成を満足にできないと、内定を得ることはできません。
15社や20社など、大量の企業に応募し、一つ一つの対策を十分に行うことができないと、どの会社からも内定が得られない可能性すらあります。従って「しっかりと対策ができる数だけ」に絞り込んで応募することを推奨します。
転職の応募数を絞るべきケース
- 時間をあまり割けない場合
- 特に志望度の高い企業がある場合
- こだわりの条件がある場合
転職の応募数の目安は5~10社程度ですが、それよりも応募数を絞るべきケースも存在します。「現職が忙しい」などの理由で転職活動に時間をあまり割けない場合は、応募数を絞り込みましょう。
志望度の高い企業があり、他の企業の志望度が低い場合は、第一志望の企業を含めて2~3社程度に絞るのも選択肢の一つです。また、どうしても譲れない「こだわりの条件」が存在しており、「この条件を満たしていない企業ならば、転職しても意味がない」と感じるほどであれば、条件を満たしている企業だけに絞っても良いでしょう。
ケース1. 時間をあまり割けない場合
転職の対策に時間をあまり割くことができない場合は、応募する企業数を2~3社程度に絞ることも選択肢の一つです。
現職が非常に忙しく、転職活動にかけられる時間が限られているにもかかわらず、一度に多くの企業に応募すると、各社への準備がおろそかになるため、内定を得ることは非常に難しいです。また、最悪の場合、現職の業務にも影響が出てしまい、査定が下がってしまうことも考えられます。
転職活動においては、志望動機や自己PRを各企業に合わせて作ることが重要ですが、多くの企業に応募してしまうと、これらがおろそかになってしまうケースが多いです。数社に絞り込み、それぞれの企業を徹底的に調査することで志望動機を練り上げ、面接対策を入念に行う方が効果的な場合もあります。
ケース2. 特に志望度の高い企業がある場合
特に志望度が高く「この企業から内定を得られたら、絶対に就職したい」と、すでに心に決めている企業がある場合は、その企業に全力を注ぐために、他の応募は数社だけに絞るという選択肢もあります。
志望動機の解像度が高く、その企業が行っている事業や今後の戦略に関しても深く理解し、しっかりと企業研究を行っていることを面接でアピールしてくる人物に対して、悪い印象を抱く企業はあまりいません。場合によっては「現時点では多少スキルが足りていない」と判断された場合でも、その熱意を買って内定を出してくれるところもあるでしょう。
このように、どうしても入りたいと思っている企業が存在するならば、他に気になる数社だけに応募を絞り、「絶対に入りたい」と思っている企業の対策に専念するのも選択肢の1つです。
ケース3. こだわりの条件がある場合
転職活動においては、自分が譲れないこだわりの条件が存在する人も少なくありません。「地元に貢献したく、どうしても地元で暮らしたい」「熱心に取り組んでいる趣味があり、絶対に土日は出勤したくない」など、こだわりの条件が存在する人も少なからずいます。
こだわりの条件がある場合、応募先を絞り込むのも選択肢の1つです。色々な企業に応募し、せっかく内定を得られたとしても、求める条件を満たしている企業でなければ意味がありません。むしろ「現職にとどまった方が自分にとって良い」と感じることもあるでしょう。
数多くの企業にむやみに応募するのではなく、こだわりの条件がある場合は、その条件を満たしている企業にだけ応募するのも選択肢の一つです。
転職で何社応募すべきか|よくある疑問点
- Q1. 同時に何社まで応募して良い?
- Q2. 1社ずつ結果を待ちながら進めるのは良くない?
- Q3. 希望の求人が少なく、応募数を増やせない場合は?
転職で「何社程度応募するか悩んでいる」という方からよくいただく質問についても回答します。転職活動を進めるにあたっての参考にしてください。
Q1. 同時に何社まで応募して良い?
まず大前提として「何社までしか応募してはならない」という制限は存在しません。自分のリソースが許す限り、応募できる数は自由です。ただし、現実的な範囲で並行して進められる企業数としては「最大で10社程度が適切である」といえるでしょう。
マルチタスクをこなすことに自信があり、「自分なら、同時に複数の企業対策ができる」と思っている方もいるかもしれません。しかし、特に働きながらの場合、複数の企業の対策を同時に行うのは想像以上に大変です。企業ごとに志望動機を作成しなければなりませんし、面接対策も一つ一つの企業に対してオリジナルなものを行わなければなりません。
前述のとおり、各企業への準備がおろそかになるレベルであれば、同時に応募するのは避けた方が良いでしょう。
Q2. 1社ずつ結果を待ちながら進めるのは良くない?
結論として、1社ずつ結果を待ちながら進めるのは、あまり推奨できません。なぜなら、並行して応募をしない場合、転職活動の期間が長引き、失敗してまた一からやり直しとなると、モチベーションを保てない人が多いからです。
1社ずつしか対策ができないほど現職が忙しい場合などは例外ですが、基本的には前述のとおり「自分が同時並行で対策ができる範囲内で」複数の企業に応募することを推奨します。
「早く終われば終わるほど良い」というわけではありませんが、転職活動があまりにも長引いてしまうと、途中からモチベーションが下がってしまうケースが少なくありません。
Q3. 希望の求人が少なく、応募数を増やせない場合は?
希望している条件を満たしている企業が少ないときは、無理に応募数を増やす必要はありません。希望している条件を満たしていない企業に転職しても、納得がいかず、再び転職を繰り返すことになってしまうからです。
しかし「希望の条件を満たしている企業が少なすぎる」「現職を続ける気があまりない」などの条件が当てはまっている場合は、自分が求めている条件の中から、妥協できるものはないか検討してみることも選択肢の1つです。
「給与」「福利厚生」「年間休日」「残業時間」「業務内容」「社風」「通勤時間」など、さまざまな条件が存在しますが、その中で優先順位が低いものを一旦外して企業を探してみると、あなたに合った企業が見つかるかもしれません。
転職エージェント「JAC」の利用もご検討ください
この記事では「転職活動において、何社応募すべきか」というテーマから、複数社に応募すべき理由や複数社を並行して転職活動を行う際の注意点、応募数を絞るべきケースなどについて紹介しました。
転職活動において1社ずつ応募することは効率が悪いため、自分が入念に対策できる範囲内で、複数社に同時並行で応募することを推奨します。しかし、現職の忙しさや、求めている条件を満たす企業の数などによっては、むやみに応募数を増やさない方が良い場合もあります。
転職エージェント「JAC」では、各業界のプロフェッショナルが個々の転職希望者様にヒアリングを行い、経歴やスキルをもとに、能力を最大限に発揮できる求人の紹介が可能です。応募企業数を絞りたい場合や、希望に合う企業が少ない場合でも、現時点で最適な求人をご紹介いたします。
また、応募書類のフィードバックや面接練習のサポートも行っているため、転職活動をスムーズに進めて、より多くの企業に応募したい方もご利用いただけます。
転職活動において応募企業の数を調整したい方や、より入念な対策を行いたい方は、ぜひ一度JACのコンサルタントにご相談ください。