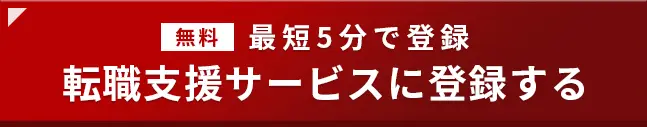ゼネラリストとしてのキャリアを歩むことを考えている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、ゼネラリストとしての力が必要とされやすい仕事や転職時のポイント・キャリアプランを解説します。
転職を検討中ですか?
今現在、
- 自分の市場価値を知りたい
- 今後のキャリアをどうするか整理したい
- 転職活動を無駄なくスムーズに進めたい
上記のようなお困りごとがございましたら、私たちJACへ相談してみませんか?
転職活動の進め方を相談する転職を検討中ですか?
今現在、
- 自分の市場価値を知りたい
- 今後のキャリアをどうするか整理したい
- 転職活動を無駄なくスムーズに進めたい
上記のようなお困りごとがございましたら、私たちJACへ相談してみませんか?
転職活動の進め方を相談する
目次/Index [非表示]
ゼネラリストとは
本章では、ゼネラリストの定義やゼネラリストと混同されることの多い「スペシャリスト」「エキスパート」「マネジメント」の3つの言葉との違いについて、解説します。
ゼネラリストとは、幅広い知識・技術・経験を備え様々なことに対応できるオールラウンド型の人材
ゼネラリストとは、広範囲にわたる知識や技術、経験を持ち、多様な状況や課題に対応できるオールラウンド型の人材のことを指します。特定の分野に特化したスペシャリストとは対極的に扱われることが多く、管理職としての役割が期待されたり、部署や業務の垣根を越えて様々な調整役を担ったりします。
ゼネラリストとスペシャリストの違い
ゼネラリストは「広く浅く」、スペシャリストは「狭く深く」と表現されるように、両者は業務範囲や役割の特性が異なります。
一般的にゼネラリストは、幅広く多様な知識や経験を身に付けたオールラウンド型の人材のことを指し、組織全体の最適化を図ったり、チームを牽引したりする役割を担います。一方で、スペシャリストは、特定の分野に特化した高度な知識・スキルを有し、自身のスキルや経験を活かし企業や社会に貢献する人材のことを指します。

-
スペシャリストとは?ゼネラリストとの違いや転職時のポイントを解説
スペシャリストとしてのキャリアを歩むことを考えている方もいるのではないでしょうか。本記事では、スペシャリストとしての力が必要とされやすい仕事や転職時のポイント・キャリアプランを解説します。 転職を検討中ですか? 今現在、… 続きを読む スペシャリストとは?ゼネラリストとの違いや転職時のポイントを解説
ゼネラリストとエキスパートの違い
エキスパートは、スペシャリストと同じ意味を持つ言葉として扱われることもありますが、使い方によっては、スペシャリストの中でも経験や実績を培い、業界の中で高い評価を受けてる人材を指すことがあります。
ゼネラリストは幅広く様々な知識やスキルを網羅的に理解し、各分野や部門を繋ぐ役割を担いますが、エキスパートは自身の習得した技術や経験を活かし、企業や社会に貢献します。
ゼネラリストとマネジメントの違い
マネジメントとは、組織やチームの目標達成に向けて、メンバーを管理したり組織を運営したりすること、またはその役割を指します。一方で、ゼネラリストは幅広い知識・スキルを活かして様々な業務に対応できる人材のことを指します。
ゼネラリストは、自らの知識や経験を活かして横断的かつ幅広い業務を遂行するのに対し、マネジメントは組織やチームを統率し、管理する役割を担います。ゼネラリストの持つ要素を活かしつつ、目標達成に向けて組織を統率する役割がマネジメントです。
ゼネラリストとしての力が必要とされやすいポジション・職種
ゼネラリストとしての力が必要とされやすいポジション・職種として、下記のような例が挙げられます。
● マネージャー・管理職
● 人事職
● 総務職
● コンサルタント
● スタートアップの社員
本章では、上記5つのポジションや職種について、なぜゼネラリストとしての力が必要とされやすいのかを解説します。
マネージャー・管理職
マネージャーや管理職は、チームや組織の掲げる目標達成に向けて、業務の進捗管理や人材採用・育成、など、チームを牽引するポジションです。例として、プロジェクトマネージャーやリーダーなどのマネージャー職や、部長や課長、店長などの管理職が挙げられます。
ゼネラリストの力が求められる理由としては、マネージャーや管理職は組織やチームを超えた横断的な連携や特性の異なる業務を複数兼任するケースが多いからです。担当する部署やプロジェクト全体の状況を把握し、各メンバーの専門性や能力、適性を理解した上で、最適な役割分担を考えたり、適切な指示やサポートを行ったりします。
人事職
人事職は、採用活動や社員教育、人材配置、評価制度の策定・運用など、企業の「人」に関する幅広い業務を担う職種です。具体的な業務としては、採用や教育、労務などが挙げられます。
採用活動においては、各部署のニーズを理解し、適切な人材を選定しなければなりません。また、従業員研修においては、時代やビジネス環境の変化に対応したプログラムを企画・実施する必要があるでしょう。このように、人事職に就くためには、人材育成に関する知見や人材採用経験、企画など、幅広い知識や経験が求められます。さらに、経営層や従業員、応募者など、様々な立場の人々とコミュニケーションを取ることが多いため、高いコミュニケーション力や交渉力も求められるでしょう。
人事職に就く場合、組織全体を俯瞰し、様々な関係者と良好な関係を築きながら「人」に関する幅広い業務を推進しなければならないことから、ゼネラリストとしての力や素養が必須となるでしょう。
総務職
総務職は、社内のインフラ整備や備品管理、社内行事の運営、危機管理業務など、企業活動を支える業務を幅広く担当します。総務職は、業務を遂行する上で、社内外の様々な関係者と関わり、多岐にわたる業務を同時に並行して行うケースが多いため、多くの企業ではゼネラリストとしての素養が求められる傾向があります。
コンサルタント
コンサルタントは、企業が抱える経営課題や業務改善の問題に対して、自身の経験や専門的な知見を駆使して最適な解決策を提案したり、施策の実行を支援したりする職種です。
ゼネラリストの力が必要とされるのは、複数の分野や業界の知識を活用しながら、最適な解決策を提案する必要があるためです。また、クライアント企業の経営戦略や現状を把握し、専門知識を活かしつつ全体像を見据えた解決策を導き出す柔軟性と対応力も求められます。
一見専門的な知見や経験だけが必要視されがちですが、コンサルタントとして活躍するためには、幅広い知識や論理的かつわかりやすく説明する能力、データ分析力など、ゼネラリストのようにマルチな力が不可欠です。
スタートアップの社員
スタートアップ企業に在籍する社員もゼネラリストとしての素養が求められることがあります。
その理由としてスタートアップ企業は人材リソースが限られている場合が多く、1人で複数の業務を兼務できるよう、自身の専門分野以外の知識やスキルも習得し、臨機応変に対応していく姿勢が求められるからです。
限られたリソースの中で多岐にわたる業務をこなしていかなければならない環境に置かれている場合、組織全体を俯瞰した行動をとれるゼネラリストとしての素養が必要になるでしょう。
ゼネラリストが時代遅れと言われる理由
ゼネラリストが「時代遅れ」と耳にしたことがある方もいるかもしれません。
本章では、ゼネラリストが時代遅れと言われる理由と今後のゼネラリストの必要性について、下記3つの観点から解説します。
● メンバーシップ型雇用からジョブ型雇用への移行
● テクノロジー普及による求められるスキルの高度化
● 今後、ゼネラリストが不要になる訳ではない
メンバーシップ型雇用からジョブ型雇用への移行
従来の日本企業では、業務や職種の範囲を限定しない「メンバーシップ型雇用」が主流であり、幅広い業務をマルチにこなせるゼネラリスト人材が評価される傾向がありました。
しかし、社会情勢が急速に変化する近年においては、顧客ニーズや市場の変化に迅速に対応するために、より即戦力となる特定の分野で高度な知識・スキルに長けたスペシャリストを求め、「ジョブ型雇用」を導入する企業が増えました。
社会情勢の変化に伴い、企業の人材採用の在り方や評価される人材の傾向が変化したことにより、「ゼネラリストは時代遅れ」と言われるようになったと考えられます。
テクノロジー普及による求められるスキルの高度化
テクノロジーの普及により、業務が高度化・専門化したことも、ゼネラリストが「時代遅れ」と言われる一因になっています。
AIの開発やデータサイエンス、ITインフラの構築など、高い専門性が特に求められる分野においては、スペシャリストのように特定の分野を極めた人材でしか対応できない業務も増えつつあります。
ゼネラリストは専門知識の不足から、活躍の場が限定されるケースが散見されるようになりました。そのため、ゼネラリストに対して「時代遅れ」というイメージを持つ人もいるようです。
今後、ゼネラリストが不要になる訳ではない
ゼネラリストが時代遅れと言われることもありますが、ゼネラリストが不要になる訳ではありません。組織を形成する上でゼネラリストが持つ能力は依然として不可欠であり、今後も多くの企業でゼネラリストが求められるでしょう。
ただし、市場動向が急速に移り変わりテクノロジーの高度化が加速する現代においては、従来のゼネラリスト像にとらわれないことが大切です。一定の専門性を身に付けた「T字型人材」や複数の専門性を有する「π型人材」など、新しい形のゼネラリストが求められつつあることを理解しておきましょう。
ゼネラリストに向いている人の特徴
ここでは、ゼネラリストに向いていると言われる次の5つの特徴について解説します。
● あらゆることに対して好奇心旺盛である
● 課題・問題に対して臨機応変に対応できる
● 多角的な視点から物事を捉え判断することができる
● コミュニケーション能力が高い
● 多くの人をまとめる経験が豊富
あらゆることに対して好奇心旺盛である
ゼネラリストに向いている人の特徴として、あらゆることに対して好奇心旺盛な人が挙げられます。
ゼネラリストには、幅広い業務への対応と多様な職種のメンバーのマネジメントが求められる傾向があるため、多岐にわたる知識や経験が不可欠です。そのため、あらゆることに対して興味を示し、新しい業務や未経験の分野にも積極的に取り組み、知識を吸収しながら業務の幅を広げられる好奇心旺盛な人はゼネラリストに向いていると言えるでしょう。
例えば、異なる領域の人々との交流を楽しみ新しい視点や考え方を吸収しようとする人や、未経験の業務やプロジェクトにも臆することなく挑戦し新たな経験を得ようとする人などが該当するでしょう。
課題・問題に対して臨機応変に対応できる
課題・問題に対して臨機応変に対応できる人も、自身の強みを発揮することで企業に貢献できるでしょう。
ゼネラリストは、特定の領域にとらわれず複数の業務を横断的に担当することが多く、その過程では予測不可能な課題や問題に直面することも少なくありません。臨機応変に対応できる人は、課題解決に向けて柔軟に対処できるでしょう。
予期せぬトラブルが発生した際でも冷静に状況を分析し迅速に代替案を検討・実行できる人や、計画通りに進まない状況においても目標達成のために柔軟に計画を変更できる人などが例として挙げられます。
多角的な視点から物事を捉え判断することができる
ゼネラリストは、企業や組織において全体を俯瞰しながら最適な解決策を導き出す役割を担うこともあり、物事を単一の視点ではなく、多角的に捉えられる力も不可欠です。多角的な視点を持つことで、主観にとらわれない判断が可能となり、より良い結果や成果に繋げられるでしょう。
各関係者の立場や意見を考慮した発言や提案ができる人や、異なる分野の知識を組み合わせて新しい発想や解決策を生み出せる人などがこの特徴を持っていると考えられます。
コミュニケーション能力が高い
高いコミュニケーション能力を持つ人もゼネラリストに向いているでしょう。
その理由として、ゼネラリストは、異なる立場の関係者の意見を調整したり、複数の部署と連携しながらプロジェクトを進行したりする役割を担うこともあるからです。
相手の立場や背景を理解しながら適切に対話を進められる人は、関係者と良好な関係を築き円滑な業務遂行を実現できるでしょう。
多くの人をまとめる経験が豊富
ゼネラリストに向いている人の特徴として、多くの人をまとめた経験が豊富な人も一例として挙げられます。
ゼネラリストは、マネージャーやプロジェクトリーダーなど、人をまとめる役割を担うこともあり、多様なスキルやバックグラウンドを持つメンバーをまとめた経験は、ゼネラリストとして活躍するにあたって強みになったり評価の対象になったりするでしょう。
ゼネラリストとしてキャリアを重ねる上で必要なこと
本章では、ゼネラリストとしてキャリアを重ねていく上で求められる下記4つの経験や素養について解説します。
● 様々な専門人材と横断的に関わる
● 固定観念にとらわれず柔軟な価値観を持つ
● 幅広い領域の知識をアップデートし続ける
● 当事者意識を持ちリーダーシップを発揮する
様々な専門人材と横断的に関わる
ゼネラリストとしてキャリアを重ねていく上では、専門的な知識やスキルを持つスペシャリストと横断的に関わる経験を積みましょう。
ゼネラリストは、組織やプロジェクトを統括する役割を担うことが多く、各分野のスペシャリストと連携し、それぞれの専門知識や技術を統合・調整しなければならない機会も多々あります。
異なる専門分野を持つ人々と積極的に交流し連携・協働することで、新たな考え方を学ぶことができるでしょう。様々な専門人材と横断的に関わる方法としては、異なる部署の人々と協働する機会を増やす、社内外の交流会や勉強会に参加するなどの方法が挙げられます。
固定観念にとらわれず柔軟な価値観を持つ
固定観念にとらわれず柔軟な価値観を持つことも、ゼネラリストとしてキャリアを重ねていく上で不可欠です。その理由として、固定観念にとらわれると、さまざまな要因が絡み合った課題や急速な変化に対応できなくなるリスクがあるからです。
柔軟な価値観を持ち、変化への適応力を高めていくためには、新しい技術やトレンドに関する情報を積極的に収集したり、異なる文化や価値観を持つ人々と交流したりして、様々な考え方や価値観を知ることが有効です。
幅広い領域の知識をアップデートし続ける
ゼネラリストとしてキャリアを積む場合、幅広い領域の知識をアップデートし続ける姿勢も不可欠です。ゼネラリストの強みは、幅広い分野に関する知識を持つ点ですが、知識が古くなると、変化する社会やビジネス環境に対応できなくなる懸念があります。
時代や市場動向を加味した判断や意思決定を適切に行うためには、ほかの専門知識を持つ人材や異業種に就くビジネスパーソンと交流したり、最新の情報を積極的に収集したりするなどして自身の知識を常に最新の状態に保つことが大切です。
当事者意識を持ちリーダーシップを発揮する
当事者意識を持ちリーダーシップを発揮する姿勢は、ゼネラリストとしてのキャリア形成に寄与するでしょう。ゼネラリストは、組織やプロジェクトを牽引する役割を担うことが多いため、当事者意識を持ち、率先して物事を進める姿勢が求められます。
日々の業務においても周囲のメンバーを鼓舞しモチベーションを高める、常に最適な方法を模索する、などの行動を意識することで、周囲からの信頼を得ることができ、より大きな仕事や責任を任せてもらえるようになるでしょう。
ゼネラリストの転職を成功させるポイント
ここでは、ゼネラリストの転職を成功させるために意識したい、次の3つのポイントについて解説します。
● ゼネラリストが重宝される企業・求人を探す
● マネジメントによって組織で成果を出した経験をアピールする
● 第三者とともに強みや専門性を丁寧に言語化する
ゼネラリストが重宝される企業・求人を探す
ゼネラリストとしての転職を成功させるには、自分のスキルセットが最も価値を発揮する企業や求人を探すことが大切です。ゼネラリストとしての能力を必要としている企業に転職することで、自身の強みを最大限に活かすことができるでしょう。
多岐にわたる業務を横断的にこなせるゼネラリストは、管理職やマネジメントポジション、業務を幅広くこなす姿勢が求められるスタートアップ企業や中小企業などの求人に着目してみましょう。
また、転職活動に取り組む際には、職務内容だけでなく、企業の理念や文化、組織構造なども確認しておきましょう。求人情報に「部署間の連携に注力している」「組織変革を積極的に行っている」などのキーワードが記載されている企業では、ゼネラリストの能力が評価されるかもしれません。
マネジメントによって組織で成果を出した経験をアピールする
マネジメント経験を持つ場合は、組織の成果創出に貢献したマネジメント経験をアピールしましょう。
アピールする際は、課題解決や業務改善、部門間調整を通じて生み出した価値や貢献を数字を用いてアピールすることがポイントです。数字を用いることで相対的に成果を示せるようになるため、成果の規模や企業への貢献度が伝わりやすくなるでしょう。
マネジメント経験がない場合でも、チームをまとめた経験や複数の関係者を調整した経験など、リーダーシップ力を発揮した経験をアピールすることで、ゼネラリストの素養を備えている旨をアピールできるでしょう。
第三者とともに強みや専門性を丁寧に言語化する
ゼネラリストはスキルの幅が広い分、アピールする強みが曖昧になりがちです。そのため、転職活動では、転職エージェントなど第三者とともに、自分の強みや専門性を丁寧に言語化することが大切です。
キャリア面談などで過去の経験を整理し、どのような場面でどのようなスキルを活かし、どのような成果を上げたのかを細かく洗い出してみましょう。
応募先企業のニーズに合わせてアピールできる強みを絞り、ゼネラリストとしての能力を具体的な言葉で説明できるようにしておくと、アピールポイントが明確になり自身の持つ強みが伝わりやすくなるでしょう。