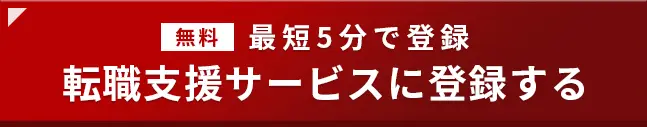「どのようなキャリアにしていくかきちんと考えたい」という方もいるのではないでしょうか。
納得感があるキャリアをイメージできるように、キャリア形成について解説します。
転職を検討中ですか?
今現在、
- 自分の市場価値を知りたい
- 今後のキャリアをどうするか整理したい
- 転職活動を無駄なくスムーズに進めたい
上記のようなお困りごとがございましたら、私たちJACへ相談してみませんか?
転職活動の進め方を相談する転職を検討中ですか?
今現在、
- 自分の市場価値を知りたい
- 今後のキャリアをどうするか整理したい
- 転職活動を無駄なくスムーズに進めたい
上記のようなお困りごとがございましたら、私たちJACへ相談してみませんか?
転職活動の進め方を相談する
目次/Index [非表示]
キャリア形成とは
本章では、キャリア形成の概要とキャリア形成と混同されやすい「キャリアデザイン」「キャリアアップ」など、キャリアに関する言葉との意味の違いを解説します。
キャリア形成とは、仕事を通じ経験・スキルを積み重ね、自己実現を図るプロセス
キャリア形成とは、仕事を通じて様々な経験を積み重ね、新しいスキルを習得しながら、自己実現を達成したり、理想の自分へと成長したりするプロセスを指します。
単に仕事に取り組むだけではなく、自身のキャリアを主体的に考え、目標を設定し、それに向かって努力していく工程のことを言います。
キャリア形成とキャリアデザインの違い
キャリアデザインは、理想とするキャリアや実現したい人生を具体的に描く行為のことを指しますが、キャリア形成は、キャリアデザインで描いたキャリアを実現するために、実際に経験やスキルを積み重ねていく行動や工程を指します。
キャリアデザインは「計画」を意味し、キャリア形成は「実践」を意味すると考えるとわかりやすいでしょう。
キャリア形成とキャリアアップの違い
キャリアアップは、昇進や昇給など、職位や収入の向上に取り組む活動や行為を指します。
一方、キャリア形成は、キャリアアップを含んだより広範な概念を指し、仕事を通して自己成長を図り、自分らしい生き方を実現することを意味します。
キャリア形成とキャリアプランの違い
キャリア形成は仕事を通じて自己実現を目指す工程を指すのに対し、キャリアプランは思い描くキャリア形成を実現するための具体的な行動を指します。
キャリアプランは、「〇年後にはどのようなポジションに就きたいか」「どれくらいの年収を実現したいか」などを時間軸に沿いながら目標達成までの道のりや行動を設定し、自身の能力をどのようにして開花・成長させていくかを考えます。
キャリア形成とキャリアパスの違い
キャリアパスは、企業が従業員に対して提示するキャリアの道筋を指す言葉です。対して、キャリア形成は企業が示すキャリアパスに沿ってスキルや知識を磨きながら、自身の掲げるキャリア目標に向かって自己成長に取り組むプロセスを指します。
キャリアパスは企業内で用意された道筋を指しますが、キャリア形成は企業のキャリアパスに沿って進むだけに限らす、個人が主体的にキャリアを設計し、自ら道を切り開いていく行動も含まれます。
キャリア形成とキャリア開発の違い
キャリア開発は、個人の能力を向上させるための学習やトレーニングを指し、キャリア形成に取り組むための手段の1つです。
キャリア形成はキャリア開発を含んだ広範な概念を指し、仕事を通じて自己成長を図り、自分らしい生き方を実現することを目指します。
キャリア形成が重要視されている理由
本章では、キャリア形成が重要視される、下記4の理由について解説します。
● AIなどテクノロジーの進化により仕事の代替が起こるから
● 平均寿命が伸び「職業人生」が長期化しているから
● 終身雇用制度・年功序列が崩壊・変化してきたから
● 働き方や仕事に対する価値観が多様化しているから
AIなどテクノロジーの進化により仕事の代替が起こるから
キャリア形成が重要視されている要因として、AIやロボットなどテクノロジーの進化により、多くの職種で業務の自動化や代替が進んでいる点が挙げられます。中でもルーチン業務や単純作業はAIに代替されるケースが増え、汎用的なビジネススキルだけでは評価されにくくなっています。
このような社会変化の中で、自分の市場価値を維持・向上させるためには、変化に対応できる柔軟な新しいスキルを自ら学び、主体的にキャリアを形成するビジネス観が不可欠です。
平均寿命が伸び「職業人生」が長期化しているから
医療技術の発展により、平均寿命が延び「職業人生」が長期化していることもキャリア形成が重要視される理由1つです。かつては、定年まで1つの会社で勤めあげることが一般的であり、職業人生も定年を機に終了するケースが通例でした。
しかし、人生100年時代に突入した現代においては、定年後の生活やセカンドキャリアを見据えた長期的なキャリア設計を考えていくことが求められつつあります。
終身雇用制度・年功序列が崩壊・変化してきたから
これまでの日本企業では、終身雇用制度や年功序列が一般的であり、新卒で入社した企業でキャリアを形成し、定年を迎えるケースが主流でした。しかし、経済構造の変化やグローバル競争の激化により、終身雇用制度や年功序列は徐々に崩壊し、成果主義を謳う企業や個人の能力を評価する企業が増えつつあります。
また、終身雇用制度や年功序列が崩壊・変化したことにより、キャリア形成の主導者が企業から個人へと移行したことから、組織に依存しないキャリア形成が求められるようになりました。
このような社会変化に伴い、キャリア形成はより重要視されるようになったと考えられます。
働き方や仕事に対する価値観が多様化しているから
リモートワークやフレックスタイム制の普及、さらには副業解禁など、働き方の選択肢が広がる中で、仕事に対する価値観が多様化している点も、キャリア形成が重要視されるようになった一因と言えるでしょう。
1人ひとりが異なる価値観を持つ現代においては、個人が主体的にキャリアを設計し、自分にとって最適な働き方を選択していくことが不可欠です。
1人ひとりが各自の目標やライフスタイルに合わせたキャリア形成の必要性を感じる社会になったことにより、一昔前と比較してキャリア形成が重要視されるようになったと推察されます。
キャリア形成のメリット
自身のキャリア形成について考えたり、思い描くキャリア形成に向けて仕事に取り組んだりするメリットとして、次の3つのメリットが挙げられます。
● 見据える未来と今すべきことが明確になる
● 自身の強みや向き合うべき課題がわかる
● 仕事に対するモチベーションを維持しやすくなる
本章では、上記3つのメリットについて解説します。
見据える未来と今すべきことが明確になる
キャリア形成を考えるメリットとして、自分が将来どのような仕事に就きたいのか、どのようなキャリアを築きたいのかといった将来像が明確になります。
行動の優先順位や取り組むべきことが明らかにになるため、最適かつ具体的な行動計画を立てられるようになるでしょう。
自身の強みや向き合うべき課題がわかる
自身の強みや向き合うべき課題が明瞭になる点も、キャリア形成について考えたり、キャリア形成に向けて日々の仕事に取り組んだりするメリットとして挙げられます。
キャリア形成について考える過程では、目指す将来像が明らかになるのと同時に、目指すキャリアを実現するにあたって不足している知識や経験、向き合うべき課題も明確になるでしょう。また、自身のキャリアや経験を客観的に分析する機会となるため、自身の強みについて知れることもあります。
自身の強みや改善すべきことが明らかになることにより、強みを最大限に活かしながら、課題に対して計画的に改善に取り組めるようになります。
仕事に対するモチベーションを維持しやすくなる
キャリア形成を行うことで、仕事に対する目的意識が明確になり、モチベーションも維持しやすくなるでしょう。日々の仕事が単なる作業ではなく、自己実現のための手段と捉えることができるようになり、仕事への満足度が高まることも期待できます。
また、自分の成長を実感する機会が増えるため、達成感ややりがいも感じやすくなるでしょう。
キャリア形成のベースとなる能力
本章では、キャリア形成のベースとなる、次の4つの能力について解説します。
● 課題を定義し解決する力
● 人間関係を構築する力
● 計画を立てやり抜く力
● 自己を理解し研鑽する力
課題を定義し解決する力
課題を定義し解決する力とは、現状を分析して本質的な問題を見つけ出し、適切な方法で解決する能力のことを指します。キャリア形成の過程においては、自分のキャリア目標に対する課題を洗い出し、適切な解決策を見つけ出す必要があるため、課題を定義し解決する力は不可欠です。
問題が発生した際に感情的にならずに冷静に状況を分析できる人や、リスクを考慮しながら最適な解決策を選択し実行できる人などは、課題を定義し解決する力を有していると言えるでしょう。
人間関係を構築する力
人間関係を構築する力とは、他者と良好な関係を築き、互いに協力できる関係を築く能力です。
良好な人間関係を築くことで、周囲からの支援や協力を得られるようになるため、キャリアの機会も自ずと広がるでしょう。
仕事は1人で完結するものではありません。多くの場合、チームや組織、お客様など、様々なステークホルダーとの連携が必要になるため、キャリア形成においても人間関係を構築する力は必須となるでしょう。
感謝の気持ちや尊敬の念を表現し良好な関係を維持できる人や、相手の意見を丁寧に聞き理解しようと努める姿勢を示せる人は、人間関係を構築する力に長けていると考えられます。
計画を立てやり抜く力
計画を立てやり抜く力とは、目標に向けて具体的な行動計画を設定し、達成に向けて粘り強く行動を継続する力を指します。キャリア形成は、中長期的な行動で築かれていくため、計画を立てやり抜く力がないと、キャリア形成の過程で挫折してしまう懸念があります。
目標達成までの道筋を具体的に計画できる人や途中で困難に直面しても諦めずに最後までやり遂げられる人は、困難な事象に直面しても最後までやり抜くことができるでしょう。
自己を理解し研鑽する力
自己を理解し研鑽する力とは、自分の強みや課題を客観的に理解した上で、自己成長に必要な行動を継続できる能力のことを指します。キャリアを形成する過程では、自分がどのような分野で価値を発揮できるのかを理解し、必要なスキルや知識を継続的に習得していかなければなりません。
周囲からのフィードバックを真摯に受け止め自己改善できる人や、目標達成のために継続的に努力できる人は、自身の置かれている立場や能力を理解し、自己実現に向けて努力し続けることができるでしょう。
キャリア形成の手順
本章では、下記一例に沿ってキャリア形成の手順を解説します。
1. 自己理解を深める
2. 最終的になりたい自分を考える
3. なりたい自分とのギャップを認識・把握する
4. ギャップを埋めるために必要な経験・スキルを考える
5. 必要な経験・スキルを獲得するための行動を起こす
自己理解を深める
キャリア形成を考えるにあたっては、まず現状を把握するために自己理解を深めましょう。
自分の強みや弱み、価値観、興味、得意・苦手などの把握に努めることで、どのような方向性やキャリアが自分に合っているのか、どのような環境で力を発揮できるのかが明らかになるでしょう。
過去の経験を振り返り、達成感を感じた瞬間や、困難を乗り越えた経験、反対にストレスを感じた状況などを具体的に分析したり、自己分析ツールや適性検査などを活用したりする方法があります。また、過去の成功・失敗体験を分析し、自分の行動パターンや思考の癖を理解することも大切です。
自己理解を深めないままキャリア形成を進めてしまうと、自分の能力や適性に合わないキャリアや環境を選択してしまう恐れがあります。自分の強みを十分に活かせず、キャリアアップの機会を逃してしまいかねません。
最終的になりたい自分を考える
続いて、最終的になりたい自分を考えます。5年後や10年後にどのような役割やライフスタイルを実現したいかを具体的に思い描いてみましょう。
例えば、ロールモデルとなる人物を探したり、長期的なキャリアプランを描いてみたりするなどの方法があります。また、プライベートも含めた人生全体を通して、自分がどうありたいのかを考えることも重要です。
本工程を怠ると、キャリアの目標が定まらないため、場当たり的な選択を繰り返してしまう可能性があります。その結果、時間や労力を無駄にしたり、後になって過去のキャリア選択を後悔したりする恐れもあります。
なりたい自分とのギャップを認識・把握する
次に「最終的になりたい自分」と「現在の自分」の間にどのようなギャップがあるのかを明確にします。目標を達成するために、どのようなスキルや経験が不足しているのか、どのような課題を克服する必要があるのかなど、ギャップの把握に努めることで、具体的な行動計画を立てられるようになるでしょう。
なりたい自分とのギャップを認識・把握しないまま、キャリア形成に取り組んでしまうと、何をするべきかがわからず、適切な行動に移せません。目標達成が遠のいてしまったり、途中で挫折してしまったりする要因になってしまうこともあるでしょう。
ギャップを埋めるために必要な経験・スキルを考える
本工程では、前のステップで明確にしたギャップを埋めるために、具体的にどのような経験やスキルが必要になるのかを考えます。どのような取り組みや経験を経ることで、必要なスキルを習得できるのかを考えることで、取り組むべき行動がより明確になるでしょう。
必要な経験やスキルが曖昧なまま行動に移してしまうと、不要なスキルや経験の習得に時間や労力を費やしてしまうかもしれません。また、具体的な行動に移せずに終わってしまう可能性もあります。
必要な経験・スキルを獲得するための行動を起こす
最後に、学習計画を作成し実行したり、転職活動に取り組んだりするなど、必要な経験・スキルを獲得するための行動を起こします。
どんなに良い計画を立てても、行動を起こさなければ、机上の空論に終わり、キャリア形成が停滞してしまうでしょう。キャリアを形成していく過程では、行動を積み重ねることが大切です。
キャリア形成のヒントとなる考え方・フレームワーク
本章では、キャリア形成において有効な次の3種の考え方・フレームワークについて解説します。
● VSOP
● Will・Can・Must
● 仕事内容・環境面・対価
VSOP
VSOPとは、「vitality/variation(活力・変化)」「speciality(専門性)」「originality(独創性)」「personality(個性)」の頭文字を取った造語であり、年代ごとに重視される経験やキャリアへの向き合い方を示すフレームワークです。
「vitality/variation」は、20代で求められる働き方やキャリアへの考え方を指し、キャリア形成に向けて「自ら様々な経験を積む」ことを推奨しています。「speciality」は、20代での経験から好きや得意・不得意を理解した上で、30代が積むべき経験として専門性を極める旨を示しています。
「originality」は、40代に求められるキャリアへの考え方を指し、30代までの積み上げた経験の中で自身の個性をキャリア形成に役立てていくことを重視しています。「personality」はキャリアの集大成として、人間力や人間性を以って事業を推進していく能力を指し、50代においては特に重要視される資質と言われています。
VSOPを参考にすることで、各年代で求められる資質や能力を理解した上でキャリアを形成していくことができるでしょう。
Will・Can・Must
Will・Can・Mustとは、「Will/何をしたいか」「Can/何ができるか」「Must/何をするべきか」の3つの視点からキャリアについて考え、次に取るべき行動を明確にするフレームワークです。
単に「やりたいこと」だけを追求するのではなく、「できること」「しなければならないこと」とのバランスを考慮することで、現実的かつ持続可能なキャリアを形成していくことができるでしょう。
Will・Can・Mustのフレームワークを利用する際は、それぞれの項目を紙やメモなどに書き出し、考えを整理してみましょう。3つの要素を整理し、重なり合う部分を探すことで、自分が本当に目指すべきキャリアが見えてきます。
仕事内容・環境面・対価
キャリア形成の過程では、思わぬ課題に直面したり、キャリア形成における軸がブレてしまったりすることがあります。キャリア形成において迷いが生じた時は、「仕事内容」「環境面」「対価」の3つに立ち返ることで、「何を優先したかったのか」「どのようなキャリアを形成したかったのか」が見えてくるでしょう。
例えば、仕事内容に重点を置く場合、興味のある分野や成長できる職務を選び、環境や対価については妥協点を見出すことで最適なキャリア選択が可能になります。
自分に合ったキャリア形成を行うポイント
ここでは、自分に合ったキャリア形成を行うために意識したい次の5つのポイントについて解説します。
● 周囲と比較したり流されたりしない
● 目指したいロールモデルを見つける
● 自分がしたくないことを列挙する
● 定期的にキャリアプランを見直す
● 今後のキャリアに対してポジティブに向き合う
周囲と比較したり流されたりしない
自分に合ったキャリア形成を行うためには、他人のキャリアと比較したり、周囲の意見に流されたりしないことが大切です。キャリアは個人の価値観やライフスタイルに基づいて形成されるべきであり、他人の成功や選択に惑わされてしまうと、自分が形成したいキャリアを見失う恐れがあります。
周囲の意見や他人の成功に流されないためには、自分の強みや弱み、興味、価値観などを深く掘り下げ、自分が何を大切にしたいのかを明確にすることが重要です。明確にした強みや大切にしたいことを基準に選択・行動すれば、自分らしいキャリアを形成できるでしょう。
目指したいロールモデルを見つける
目指したいロールモデルを見つけることで、キャリア形成における指針が具体化するでしょう。
ロールモデルとは、目指したい人物像のことを指し、ロールモデルの行動や考え方を参考にすることで思い描くキャリアに近づくための行動がとれるようになります。
ただし、ロールモデルの考え方や行動を参考にする際は、完全に模倣することは避け、自分の個性を活かすことにも意識を向けましょう。
自分がしたくないことを列挙する
キャリア形成では「したいこと」を考えるのと同時に、「したくないこと」も明確にしておきましょう。
過去にストレスを感じた業務や避けたい労働環境など、過去の経験や価値観に基づいて自分がしたくないことを列挙することで、自分に合わない選択肢を排除し、より適切なキャリアを築くことができるでしょう。
定期的にキャリアプランを見直す
キャリアプランは、状況や価値観の変化に応じて定期的に見直しましょう。
ライフステージや社会環境が変わる中で、過去に立てたキャリアプランが現状に合わなくなることも珍しくありません。定期的に見直すことで、常に変化に適応したキャリアプランを定めている状態になるでしょう。
キャリアプランを設計した際は、半年や1年ごとなど、キャリアプランを見直す時期を決めておきましょう。キャリアプランを見直す際は、現在の状況や達成できたこと、変化したことなどを振り返り、今後の目標や行動計画を修正します。時には、転職エージェントなどキャリア形成を支援するプロに相談し、客観的な視点からアドバイスを受けるのも良いでしょう。
今後のキャリアに対してポジティブに向き合う
キャリア形成の過程では、困難や予想外の出来事に直面することもあります。しかし、そのような状況こそ、新たな学びや成長の機会になるかもしれません。そのため、常にポジティブな姿勢で向き合うことを意識しましょう。前向きな姿勢でキャリア形成に取り組むことで、失敗から学び、次の挑戦に活かせるようになるでしょう。
キャリアに対してポジティブに向き合うためには、達成感を得られる短期的な目標を設定する、成功体験や小さな成長を定期的に振り返り自分を肯定する習慣を持つなどの取り組みがあります。
キャリア形成の支援サービス
1人では思い描くキャリア形成を実現できないと悩む場合は、キャリア形成を支援してくれるサービスを利用するのも1つの方法です。
本章では、キャリア形成を支援してくれる、下記3つのサービスについて解説します。
● 厚生労働省のハロートレーニング
● JACのキャリア形成イベント・セミナー
● JACのコンサルタントによるキャリアプラン面談・キャリアの棚卸し
厚生労働省のハロートレーニング
ハロートレーニングとは、希望する仕事に就くために必要な職業スキルや知識の習得を支援する公的制度です。
受講対象者は、キャリア形成に向けてスキルアップを目指したいと考える在職者や、転職に向けて新たなスキルを習得したい転職希望者など、働く意欲を持つ人材全てであり、次の5つから受講時点の状況に適した訓練を受講できます。
● 離職者訓練
● 求職者支援訓練
● 在職者訓練
● 学卒者訓練
● 障がい者訓練
離職者訓練もしくは求職者訓練を受講する場合、原則受講料は無料です(テキスト代のみ自己負担)。学べる技術やスキル、難易度は多岐にわたるため、キャリア形成に向けた一助となるでしょう。
JACのキャリア形成イベント・セミナー
JACではキャリアを考える上でヒントになる、イベントやセミナーを定期的に開催しています。
業界別のキャリア相談会や企業対談、キャリア形成の一助になるセミナーなど、多様なイベントが開催されています。キャリア形成の過程で悩みが生じたり、キャリア形成の目標を考えたりする時にご視聴・ご参加いただくことで、新たな気付きを得られることもあるでしょう。
キャリア形成における悩みの解消につながったり、目指すキャリア形成を実現するための手助けになったりすることもあるでしょう。
>>JAC Recruitment 転職イベント・セミナー情報
JACのコンサルタントによるキャリアプラン面談・キャリアの棚卸し
思い描くキャリアを形成するにあたっては、キャリア形成や転職支援のプロである転職エージェントの力を借りるのも1つの方法です。JACでは、コンサルタントによるキャリアプラン面談の実施やキャリアの棚卸しのサポートを提供しています。
多くの方々のキャリア形成を支援してきたJACのキャリアプラン面談を活用すれば、現在地と将来像とのギャップが明確になり、キャリアを形成するにあたって必要な行動が明確になるでしょう。また、JACのコンサルタントとともに、キャリアやスキルの棚卸しを行う際には、キャリア形成に取り組むにあたって有益なアドバイスを得られることもあるでしょう。
キャリア形成について悩みや課題を抱えている方は、ぜひJACが提供するキャリアプラン面談やキャリアの棚卸しをご活動ください。